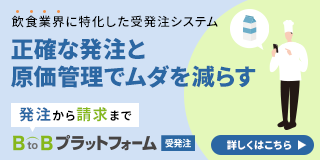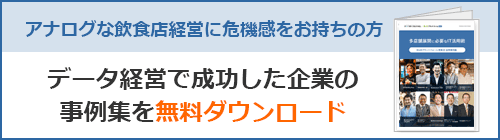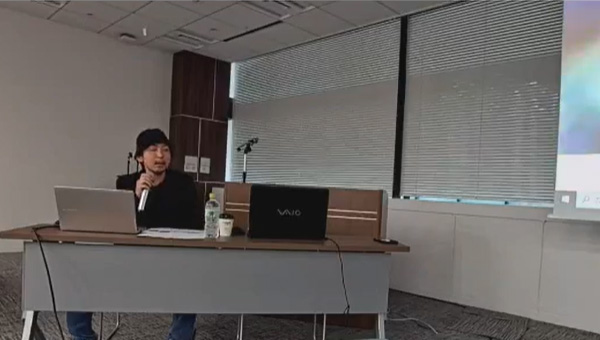第1部:ゲスト講演~青二才でやってきたこと、やりたいこと~株式会社青二才 代表取締役 小椋道太氏
同社は2007年に創業し、東京・阿佐ヶ谷に「青二才」をオープン。「日本酒をカジュアルに」をモットーに、日本酒をワイングラスに注ぎ、少量から楽しめるカジュアルなスタイルを打ち出し、日本酒の新しい楽しみ方の可能性を広げてきた。
2013年に東京・中野に「青二才」を、2015年には「神保町 青二才」を開店する。同じ年に1号店が建物老朽化のためやむなく閉店したものの、2016年に会員制「阿佐ヶ谷 青二才」、2020年には中野の既存店近くに「青二才はなれ」をオープンし、いずれも日本酒を専門とした店だ。
筋を通しつつ、マイペースで

代表取締役 小椋 道太 氏
株式会社青二才 代表取締役 小椋道太氏(以下、小椋):青二才という店を始めてから15年になります。その間、テーマにしていたのはなんといっても「人」です。お客様、スタッフ、業者、そして僕自身がいかにこの会社と関わっていくか。それを模索しながらやってきました。
もっと言えば人間社会に対して、とにかく筋を通した会社でありたいなと。「今後会社としてどう発展していくか」も大事ですが、それよりは「このやり方間違ってないよな?」「誰からも応援してもらえる選択だよな?」という視線を持っていたいと考えています。
毎晩来店客と楽しんでいる父の姿
小椋:子供の頃に田舎で父が飲食店を出し毎晩お客様と楽しそうにしている姿を見ており、それ以外の仕事を知らずに育ちました。やがて、自分も東京に出て、父と同じように飲食店で働きます。ところが実家の店と違い、料理長、ホール担当、酒担当、さらに経営者がいて、すべてが分業化されていました。東京ってすごいなあと思い、さらに魅せられていきます。
大学卒業後は知り合いの独立に付き合い飲食の会社に入りましたが、そこですぐに気付いたのです。東京で店をやりたいと言いながら、この給料と拘束時間では、45歳ぐらいで郊外の駅から15分ほどのカウンターだけの店で細々とやっていくしかないだろうなぁと。せっかく東京に出てきて、これが本当に正解なのかなと。
思い付きで始めた花見形式から間借り営業、そして1店舗目の開業へ
小椋:葛藤の中で、まったくの思い付きから、ヘンなことを始めました。暖かい時期だけでしたが、毎週日曜日や休日に、東京・吉祥寺の井の頭公園に焼酎を30本ぐらい運んで、20畳ほどのブルーシートを敷いて並べ会費を取る形で開き、これを3年間続けました。人脈も経験もお金もありませんでしたが、僕のゴールは自分でお店を持つこと。楽しい経験でしたが、このままじゃ駄目だという意識はずっと持っていました。
その後、東京・三鷹で知り合いがやっている店が休業となる日曜日に、間借りして居酒屋を始めました。最近流行りの二毛作スタイルです。18坪の狭い店でしたが、公園に集まっていた人たちが、初日から100人ほど集まってくれました。そのうち、毎週のように店が満員電車のようになり、奥のお客様にはバケツリレーでお酒を届けてもらう状態でした。
1年後の2007年、27歳のときに阿佐ヶ谷に1号店となる「青二才」をオープンしました。実際には飲食店としての知見はなく、メニューは数点程度。それでもドリンクだけは、ビール、日本酒、焼酎、カクテル、ワイン、リキュールなど300アイテムは揃えました。そんなスタートをし、次にどんな業態の店をやろうかという発想もなく、2店舗目を出すまでに時間かかってしまいました。
2店舗までの5年間=知見を掘り下げる期間
小椋:いざ2店目をやろう、となったのが2012年。それまでの間にドリンクとして提供するものを掘り下げました。ビールなら、当時「地ビール」と呼ばれていたクラフトビールを勉強し、ワインも勉強会に行き知見を広げました。なかでも面白いと思ったのが日本酒でした。
日本酒は不思議なお酒で、関連イベントを行うと大勢の人についてきていただけるんです。右肩下がりの日本酒業界からも、熱い人たちが応援してくれました。まずお客様が反応してくれ、次に酒販店さん、最後には蔵元さんも応援してくれました。
次はぜひ日本酒でいこうと、2013年に東京・中野のレンガ坂に「日本酒バル 中野青二才」をオープンさせました。定額・少量で楽しむことができ、おしゃれなシャンパングラスで飲め、日本酒に詳しくなくても雰囲気を伝えてオーダーできる、というコンセプトで営業しています。
コロナ禍での激動の2年間
小椋:出店を重ねてきましたが、2020年からの2年間は大変でした。大好きで大事な飲食ですが、これを堂々とできなかったのです。店を開いていれば、例えば医療現場をひっ迫させてしまう。本当に自分たちが正しいことをしているかどうかの自問自答を繰り返しました。行政とも話し合いを続けて、迷いに迷った挙句、要請に従いながら、行政の許す範囲内での営業を続けました。
そのなかでも、チャレンジしたことがありました。中野のレンガ坂にある飲食店と協力して「レンガ坂デリバリー」を始めたのです。いろんな店のメニューが混在していて一つで何店舗もの味が楽しめる弁当を配達して回るのです。
面白いプランでしたが、結局はUberさんなどと比べて人件費も手間もかかってしまい、長続きしませんでした。ただ、一つのものに対してエリアでチームが組めたことは素敵な体験でした。
日本酒を救え!
小椋:コロナを経て大事な教訓になったのが日本酒の存続です。日本酒とお客様をつなぐのは、コンビニやスーパーではなく、やはり居酒屋です。だから、コロナで宅飲みが主流になると、日本酒より手軽に入手できるビールや酎ハイにお客様が流れてしまう。
一方で、清酒を造る免許は、財務省管轄の酒税法でガチガチに固められていて、新しく蔵を作るのはほぼ不可能です。いまある蔵元の数が、この先減ることはあっても増えることはありません。
このままでは酒蔵は減る一方で、外国資本が入るとなると寂しくもあります。そこで僕は酒販免許を取りました。日本人はことのほか季節の移ろいに敏感で、春には春の酒、夏には夏の酒があり、ほかの季節には売れません。酒販免許があれば、それを「半年寝かせた」とうたって再販することが可能になります。
これもやはり本業の酒屋さんにはかないません。酒蔵をつぶさないための小さな支援として、細々と続けていこうと思っています。
未来にむけてどう動いていくか
小椋: 2021年11月、中野に「角打ち割烹 三才」というお店を出しました。特別感のある12,000円のお任せコースを提供する割烹と、ふらりと立ち寄れるカジュアルなバルスタイルの角打ちの2つにゾーニングしたお店です。
コロナ禍以降、飲食店は「いい店があったから入る」のではなく、「あそこに行こう」と思わせるお店でないといけない、と考えるようになりました。それで立ち上げた店が「各内割烹 三才」でした。
また、同年12月には中野にほど近い新井薬師に「YAKISOBA JOINT一服」をオープンしました。ここは進化系焼きそば専門店として営業するほか、店内奥はセントラルキッチンとして、レトルト食品を作っています。ほかの飲食仲間が作ったメニューをレトルトにすることで、コンビニやスーパーで売れるようになります。
先ほども触れましたが、飲食業界にいても結婚や出産などで離れざるを得ない人たちとも繋がっていたい。そう人たちに働いていただく場としても機能させていきたいと思っています。飲食業界を支えるのは、やはり「人」だと信じているからです。