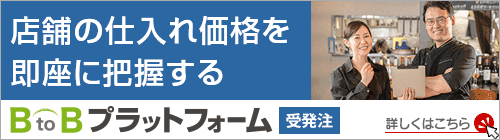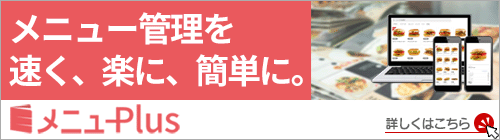本格イタリアンなど90種類以上を時間無制限で食べ放題
【Q】PISOLA(ピソラ)は、テレビでもたびたび紹介されるほど人気ですね。

株式会社ピソラ 商品本部 商品本部長 レフェイブ 和矢 氏(以下同):当社はイタリアンレストラン「PISOLA」を、直営37店舗、FC16店舗展開しています。バリ島のビーチクラブをイメージした店内で、幅広いお客様にご来店いただいています。
石窯焼きのピッツァや生パスタ、リゾットなどの本格的なイタリアンを中心としたフードメニュー約90種類を、3,628円(税込)から時間無制限・食べ放題でお楽しみいただけます。他にも、食べ放題ではご注文できない本格的な料理もラインナップしています。
【Q】食べ放題スタイルは原価管理が難しいといわれています。

お客様がお好みの料理を選べる食べ放題業態は、食材の消費量を正確に予測することが困難です。食材の過剰な仕入れや廃棄のリスクが高く、お客様の来店人数や滞在時間によっても消費量が大きく変動します。また、原価の高い食材を多く使用するメニューは、利益に大きな影響が出てしまいます。
当社でも多種多様なメニューをご提供しているため、原価の管理が複雑です。コロナ禍の頃は、食材原価の高騰で原価率が29%から33%まで上昇したことがありました。原価率はたとえ0.1%の誤差でも、全店舗を合計すると毎月数百万円の損失につながりますから、早急に対策する必要があったのです。
仕入データ・販売データを組み合わせ、原価率33→28%に改善
【Q】どのような取り組みをされたのでしょうか?
原価高騰や食材ロスの対策には、データによる現状把握と分析が何より重要です。当社では、インフォマートの『BtoBプラットフォーム 受発注』や『メニューPlus』、店舗管理システムから様々なデータを紐づけることで、適正な仕入れや調理オペレーションを確立し、仕入れの最適化と利益の向上を実現しています。大きく分けて4つの取り組みを行いました。
(1)食材ロス金額の算出による現状把握
メニューごとの理論原価と実原価を把握して、乖離が大きい場合は仕入品を見直すなどの対策をしています。
理論原価は『BtoBプラットフォーム 受発注』で仕入品ごとの金額を集計し、『メニューPlus』とデータ連携させて算出します。
また、食材ロスを減らすために店舗ごと、曜日ごとに必要な仕入品の数量・仕込み量を予測して、発注や仕込みをしています。
店舗管理システムから得られたメニューごとの販売実績と、『BtoBプラットフォーム 受発注』から得た仕入品・仕入金額、『メニューPlus』から得た仕掛品の原価・メニューの原価をもとにして、算出するのです。たとえば、トマトソースが平日9缶必要で、在庫が3ある場合、6缶だけ仕入れるようにしています。
そして、店舗ごとに発生した食材ロス金額を毎日収集しています。仕入品や仕掛品の品目、単価をリストアップしておき、各店が営業終了後に廃棄したアイテムの数量を入力することで、金額を自動計算する表を作成しました。こうしたデータを定点観測することでロスが多い店舗が特定できるので、原因と対策が見えてきます。
たとえば、冷凍肉で解凍ロスが発生しているとします。解凍する際の最低ロット数が大きすぎるのではないか、などと仮説を立て、仕入品を1パック500gから300gの商品に変更するなど、適正な仕込み量を把握して廃棄ロスを軽減するよう務めています。
(2)仕入れの見直し
次に、仕入れ上位の商品について、仕入先と価格交渉をしています。『BtoBプラットフォーム 受発注』で取引数量を集計し、仕入れ上位品目の影響度を分析しました。
たとえば、トマト缶を切り替える際、どのくらい原価率に影響が出るかを調べます。『BtoBプラットフォーム 受発注』の仕入れ実績データをダウンロードし、店舗ごとに単価を置き換えることで、前後比較をしています。
また、『メニューPlus』で原材料を変更した場合の原価の変化も確認しています。たとえば、マルゲリータのトマト缶を変えることで、原価が100円から70円になったとします。この場合、1食あたり30円の原価削減になりますが、月間の販売数と掛け合わせることで、店舗全体でどのくらい影響があるのかを把握できます。この分析をもとに、特に使用頻度が高い上位10品目に対して、メーカーに直接交渉を行っています。
交渉する際は、単に安価な商品の切り替えを相談するのではなく、当社がレストランとして地域のお客様に届けたい思いやビジョンをお伝えし、「その達成のためにご協力いただけませんか」とお話しています。結果的に、同等の商品をより安価に仕入れられるようになりました。
(3)レシピ・調理オペレーションの見直し
レシピの分量調整と調理オペレーションの改善も功を奏したと思います。たとえばブレンドオイルの配合比率を変更したり、プチトマト1個を半カットから4分の1カットに変更したりなど、細かな改善を繰り返しました。
他にも、オーバーポーション対策としてモッツァレラチーズは目分量でなく計量を徹底させたり、明太子を計量スプーンでとった際、スプーンに付着した分がロスになっていたので、調理器具をディッシャーに変更したりしました。
ベーコンは使用頻度が高く原価も高いので、1食の使用分量を20gから6本に変えました。わずかな違いですが、“塵も積もれば山となる”です。こうした細かな点を調理マニュアルに反映しています。
(4)売価変更をルール化し、メニューの見せ方を工夫
こうした取り組みを徹底したうえで、最後が売価変更です。『メニューPlus』で集計した原価率が高いメニューを検出し、一定以上に上がったら売価を調整するというルールを運用しています。同時に、メニュー表のデザインも工夫しました。たとえばマルゲリータピザにチーズをトッピングする際、「プラス100円」と表記してお得感を演出するなど、原価率をコントロールしながら顧客単価を上げる取り組みを行いました。
このようにコントロールすることで、毎月の理論原価と実原価の乖離を2%以内に抑えています。原価率は当初の33%から28%に改善しました。ITツールを使うことであらゆるデータ集計が即時にできます。問題を細かくドリルダウンすることで原因が特定しやすくなり、効果的な対策につながったと思います。
データドリブンな原価管理で、顧客満足度を追求したい
【Q】今後の展望をお聞かせください。
当社では原価のコントロールや食材ロス対策を徹底して取り組んでいます。一方で、お客様が当社の時間無制限・食べ放題メニューを安いと感じるか高いと感じるかは、商品やサービスによって大きく左右されます。重要なのはコストパフォーマンス。今後も単なるコスト削減ではなく、食材の活かし方を工夫し、お客様にこの価格でこのクオリティはすごいと思っていただけるようなメニュー開発に力を入れていきたいです。
株式会社ピソラ
本社所在地:滋賀県草津市東矢倉1-5-2
設立:2019年9月(創業2004年10月)
代表者:代表取締役 鬼界友則
公式ホームページ:https://pisola.jp/