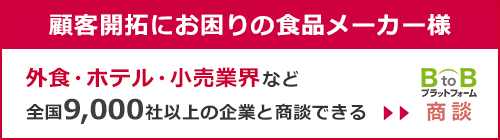炒飯が家庭に広がると、町では喫茶店や洋食店といった、本格的な中華料理店ではない業態でも炒飯を提供するようになる。
そこで、発売から5年後の1962年には業務用「炒飯の素」も開発。個人経営で切り盛りし、サイドメニューに手間をかけられない店主たちのニーズに応え、多いに歓迎された。
「当時の市場規模は約3億円。競合はなく、あみ印の独壇場でした。テレビも一般家庭に広 がる前の時代です。当時、ラジオで放送されていたドラマを1社で提供して「炒飯の素」を宣伝しました。

神山栄里子
その電波の届く東日本を中心に東北、北海道と商品を流通させたところラジオのコマーシャルを聞いたお客様が乾物屋に殺到したそうです。
問屋さんから『おかげで販路が拡大できて“炒飯の素御殿”が建てられました』と言われるほど売れていたと聞いています」(販売促進室チーフプロデューサー・神山栄里子氏)
食の多様化、大手の参入、それでもあえて「変わらない」
高度経済成長が終止符をうつ1970年代になると、国民の食生活にも変化が起こる。外食ではファミリーレストランやファストフード店が次々オープン。カップ麺も登場し、食は家庭料理やコメ食だけではなくなってきた。また、保温機能をそなえた電気炊飯器も一般的になり、冷やごはんを炒飯に作りなおす需要も減る。
さらに他社競合品も少しずつ出はじめ、市場を侵食しはじめた。トップシェアは保ち続けていたものの、炒飯の素の売上は縮小していった。

決定的だったのは、大手食品メーカーの相次ぐ参入だ。調理の手間をより省く「乾燥具材入りの炒飯の素」が、大々的なテレビコマーシャルと共に発売され、市場は一気に拡大した。主流はまたたく間に「具材入り」となり、あみ印は売り場の棚を、トップメーカーの座ごと奪われてしまった。
「当時、やはり考えたと聞いています。うちも具材入りをつくるべきなのではないかと。しかし、売るためのリニューアルをするか、作ること自体やめるかも含め、度重なる検討の結果、パッケージも中身も発売当初のままで継続販売することを会社の方針として結論づけたのです」(小池氏)
それは「味はお客様が決めるもの。メーカーが変えてはならない」という創業以来のポリシーに基づく決断だった。

「どんなに大手メーカーが売り場に攻勢をかけても、縮小したとはいえ弊社の棚は消えませんでした。それは買ってくださるお客様がいるということです。もう売上の伸びは期待できなくても、その期待にはお応えし続けなければなりません」(小池氏)