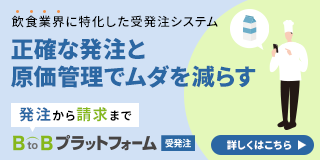多彩な客層を受け入れた、「餃子とビール」の鉄板アイテム
「調布でやっていたダイニングバーは客単価4000円ほどの洒落た店で、客層は20代後半から30代のある程度稼いでいる独身者がほとんどでした。ただ、調布駅の1日の乗降客数は11万人以上で店から1km圏内には5万人もの人が住んでいるのに、なぜ限られた層のお客さんしか来ないのかを常に考えていました」
駅から少し離れた住宅街で店の認知度も低い、特化したメニューがないので来店動機が生まれにくいなど、理由はいくつか考えられた。そんな中、井石氏の頭の中には「餃子とビールではどうだろう。誰にでも親しまれやすいのではないか」というイメージが芽生えていた。

ジューシーな肉汁があふれ出す
「僕もそうなんですが、餃子が好きな人はたくさんいると思います。ただ、餃子を食べながら堂々とお酒を飲めるお店って、ありそうでなかったんです。おじさんが一人で行くような街の大衆中華ならありますが、若い人や女性は入りづらいですよね。餃子とビールは鉄板の相性だと誰もが思っているなら、それを気軽に楽しめる店を出せばいろんな人に来てもらえるんじゃないかと」
誰もが認める鉄板アイテム「餃子とビール」を軸に据えた新しい業態への挑戦。看板となる餃子の開発には1年を要したが、7年間のダイニングバー時代に毎月新メニューを作り続けてきた経験を生かして、「日本一」を自称する納得の味にたどり着く。
また、店づくりに関しても並々ならぬこだわりをもっていた。
「飲食店、特に路面店として出すお店は、その街の顔にもなるわけです。だから、老若男女あらゆる方に来ていただけるような、間口の広い店づくりにこだわりました」
幅広い客層に向けた店づくり。それは、ともすれば個性のない凡庸な店になってしまう恐れもある。ところが、井石氏はファミレスと居酒屋の中間とでも言うべきスタイルでそれを実現したのだった。
「餃子とビールを基本に据えながら、持ち帰りの餃子があれば普段あまり外食をしない主婦の方にも使ってもらえるし、ランチをやればあまりお金のない学生さんにも来てもらえます。あとは、アイドルタイムの時間帯でも、お通し無しで餃子とビールを提供できればご年配の方も使えるはずだと考えました」
この思惑は、そのままずばり「ダンダダン酒場」で的中している。実際に、記者が平日の昼下がりに京王線沿線の店舗を訪れてみると、井石氏の話どおりの光景が広がっていた。
地元の幅広い客層から受け入れられた「餃子とビール」の店。その魅力は他の街にも広がり、その街と一体になって輝きを増してゆくこととなる。
「街を変えた店」を支える、独自のスタッフ教育
取材も終盤に差しかかった頃、これまでの道のりを振り返るように井石氏の話に頷いていた田中氏が熱っぽく話してくれた。