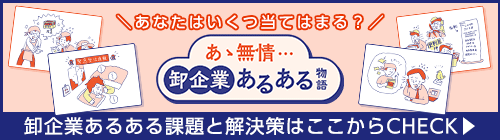放っておけない食品卸業界の課題

営業本部マネージャー
伊藤裕哉氏
コロナ禍の影響が薄れつつある中、消費者の外出傾向が高まり、飲食店の需要が回復してきた。一方で、食品卸業界では原材料や原油、電気などの高騰、人件費の上昇、労働者の採用難といった課題が継続して残っている。
CBcloud株式会社営業本部マネージャー 伊藤裕哉氏(以下同)「特に、クール便などを活用する荷主にとって、1個当たりの単価が高まり、利益の確保が難しくなっています。業界の各企業がDX、生産性向上、品質改善などさまざまな観点で見直しを行っていますが、事業全体の最適化には至っておらず、部分最適の状態にとどまっているのが現状です」
食品卸業界の3つの課題である原材料・燃料コスト高騰、人材不足、生産性について見ていこう。
食品卸業界の課題1~原材料・燃料コスト高騰
世界的な人口増加による食品の需要増加、干ばつなどの天候不順、原油高、日本の円安などが重なっていることで原材料や燃料の高騰が起きている。日本では道路貨物輸送や海上貨物輸送など物流業界全体で運賃が上昇傾向にあり、売上高に対する物流コストの比率も上がっている。この傾向は2024年も引き続き継続する見通しで、いかに持続可能性の高い物流網を構築するか、バックアップできる制度を作るかが重要になってくるだろう。

食品卸業界の課題2~人材不足
商品の配送をする事業者において、自社便や外部委託を問わずドライバーの人材不足は深刻な問題だ。今後も卸売業の求人倍率の回復は見込めないといわれている。事業者には長時間労働などの労務環境の改善に加え、人材の確保と定着化の戦略が必要になる。
また、年齢構成比を見ると、運送業は10~20代の若手人材が他の産業に比べて少ない。この背景には、若手が就きたい仕事になっていないといった課題があるといえる。

食品卸業界の課題3~生産性と品質
大型・中小型トラックの年間労働時間は、全産業の平均よりも2割ほど多い水準だ。その要因は荷待ち時間などの非効率的な業務である。解決の糸口としてITを活用したDX経営が考えられる。
「人の作業が介在する場面では、ミスの発生が避けられません。また、業務が特定の個人に依存して属人化が進むと、運用の柔軟性が下がり、持続可能性に影響を及ぼします。
DXの例として、受発注サービスは受注ミスによる再配達の改善や業務時間の削減において効果を発揮しますし、配送業者のマッチングサービスは配車業務を迅速かつ確実に行えます」
その他の課題では、2023年10月に導入されたインボイス制度も食品卸業界に影響を及ぼすと予想される。物流の現場を支えているのは、幹線については比較的大手の運送事業者であるが、飲食店や小売店などへの配送は中小の事業者や個人事業主によって担われていることが多い。インボイス制度の導入で中小事業者の負担が増加し、経営を圧迫する可能性がある。この状況が継続すれば廃業に追い込まれる業者が増え、結果的に商品の配送にも支障が生じると考えられる。
働き方改革法案と2024年問題
2024年4月に適用される働き方改革法案は、2024年問題として物流業界に大きな変化をもたらすといわれている。その内容は、自動車を運転する業務の時間外労働を年間960時間に制限し、月60時間を超える時間外労働に対する賃金の引き上げが実施される。

この法改正により、運送会社や物流部門の人件費増加、1配送あたりの売上減少、ドライバーの賃金減少などが起こりえる。各企業はドライバーの担い手不足を防ぐために2023年4月頃から運賃の引き上げを検討し、実施する交渉を行っているという。
「社員の採用には約90日かかると言われており、2024年問題に対応する時間は限られています。さらに将来的には配送需要の増加と供給の減少により、2027年におけるドライバーの不足は24万人に上ると予測されています」
2024年問題により悪化すると予想される4つの課題
2024年問題の影響をはじめ、今後の物流業界では4つの課題が深刻化すると言われている。
1. トラック輸送のリソース減少
働き方改革関連法によりトラックドライバーに対する時間外労働時間の上限が年間960時間に制限される。これにより運べる距離と時間が減少し、運べる物量も制約される。
2. EC化率の上昇と荷物の小口化
eコマースやネットコンビニ、ネットスーパーからの購入増加している。宅配便の取扱数の増加と荷物の小口化が進み、物流現場がますます逼迫し、積載効率が減少する。
3. 採用難と高騰する経費
運送業における採用難と高齢化が顕著になる。世界・社会情勢によるガソリンの高騰で運送費用が大幅に増加し、物流業界に圧力をかける。
4. 買い物難民・物流難民の増加
積載効率や不採算ルートの削減で、過疎地域を中心に買い物難民・物流難民の増加が懸念される。
「多くの企業がドローンなどを活用した実証実験を行っていますが、荷物の小口化が進行しているため、ドローンで運べる荷物のサイズや数量には制約が生じます。各課題は連動性があり、統合的に解決していく必要があるでしょう」
物流業務の改善への取り組み事例
現在行われている物流業務の改善への取り組み事例を紹介する。
事例1~フィジカルインターネットによる積載率の向上
共同配送による積載率を向上させる取り組み『フィジカルインターネット』は数年前から提唱され、現在も進行している。

経済産業省は荷主と配送業者のマッチングサービスを利用することが積載効率向上に有効と述べている。国が主導している産学連携により位置情報や荷物情報などを連動させ、新しい物流システムの構築を考えている。この課題は単一の企業では実現できないため、物流関係者の協力が必要だ。
事例2~同業界、同企業内で多数の荷物を共同配送する仕組み
近年、営業用トラックの積載効率は40%未満に低下し労働力不足の要因になっている。
同業界や同一企業による共同配送の仕組みも各社で連動している。ハウス食品グループなど食品メーカー6社が同業種で同様の配送が行われるため、共同配送する仕組みを構築している。セブンイレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートなどでは一部エリアで共同配送の実証実験をした。
「同業界における共同配送の仕組みは一部のエリアで進められていますが、全国的に普及すべきでしょう。物流の改善のためには、競合する企業同士が垣根を越えて、物流構造自体を変えていく取り組みが必要になると考えられます」
事例3~待ち時間の解消
運行当たりの待ち時間は、1時間超えが5割以上だ。長時間労働がドライバーの負担となり、担い手が減少する要因となっている。これは夜間に長距離運転と納品を行う物流業界特有の問題であり、荷捌きをいかに効率化するかが重要だ。

荷物の小口化に伴い、荷物を手積みや手降ろしすることが増えている。車格を見直して積荷に合ったトン数や装備品を改善することで、待ち時間を200時間減少させられる可能性もある。
長野県の食品卸企業の間では、荷待ち時間を短縮する各社の実験が始まった。物流拠点内での動線を改善、ロボット導入による省人化を進め解決を図る。
また、マルハニチロ物流は、トラック予約受付サービスを利用しトラック車両の待機削減を目指した取り組みを進めている。
ITツール導入による業務の改善
人手不足の課題を抱える企業は、できるかぎり業務を効率化し属人化を解消することが望まれる。それにはデジタルツールなどの仕組みを取り入れることが解決策となる。
「企業が人手不足を改善するには、ITを使って労務環境を整備し自社の採用力を強化するかと、外国人採用の推進することだと思います。また、生産性向上も必要になります。業務を効率化し、特定の人に頼らず標準化することが解決につながります」
物流に関わる人材が不足している分、ITを活用して補っている企業が増えてきている。2024年問題の解決策のひとつとして検討してみてはいかがだろう。