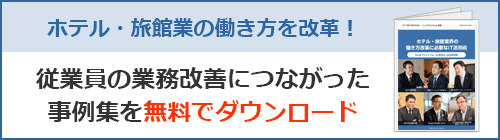モチベーションと報酬~全産業で下位の報酬をいかに上げるか
ロイヤルホテル(大阪府大阪市)取締役会長・日本ホテル協会 副会長 蔭山秀一氏(以下、蔭山) 当社ではモチベーションに大きく影響するのがコミュニケーションであるという前提に立って、全社で社内チャットツールを導入しました。あわせてメンター・メンティー(指導する者・される者)を明確にし、先輩後輩との間で徹底的に指導し教育する体制を整え、さらにグループホテルとの交流研修を積極的に実施していくことにしました。しかし、なかなか成果が見られませんでした。

日本ホテル協会 副会長
蔭山 秀一 氏
そんなときに外資系ホテルの人事システム、給与システムの仕組みに触れる機会があったのです。そこで気付かされたのが、我々がいかに遅れているかということでした。
宿泊業界では、専門性を高めることを目的に部門間の移動をせず、評価基準も明快に定めず、年功や勤続年数によって給料の差をつけてきました。リーダーシップ研修でも本当の意味でのリーダーシップとは何かという研修をせずにマネージャー、部長の任命もしてきました。
一方、外資系のホテルは至極明快に業務の内容が明示され、役職ごとに必要な要件が定義されています。そこを固めずして、従業員のモチベーションを上げるようなシステムの提供はできないのではないか。社員のモチベーションを上げるには、会社自身に大変革が必要であると捉えて、その作業をしているところです。
鶴雅ホールディングス(北海道釧路市)代表取締役社長・日本旅館協会 会長 大西雅之氏(以下、大西) 従業員のモチベーションを向上させるのは、なによりも宿泊業の魅力である接客の喜びを伝えるのが大前提と考えています。一方で、従業員の基本的な所得水準や住環境の確保も重要です。
2022年の産業別年収データを見ると、サービス産業の年収は全産業10区分の中で下から2番目です。さらにサービス産業16区分の中で、宿泊業は残念ながら下から2番目です。宿泊業の給与水準はサービス産業の平均値から16%も低い状況なのです。
宿泊業に従事する社員に希望と誇りを持って働いていただくには、サービス業全体の平均給与を上回る必要があります。私は旅館協会の会員に、まずは自社の給与を3年間で16%アップしようと働きかけています。もちろん16%の人件費アップは、黒字の旅館に限定した平均的な経常利益の額とほぼ等しく、大きな痛みを伴います。
従業員の給与を上げるには、例えばサービス料を復活させて単価を上げるなど、旅館業界全体で仕組みづくりに取り組む必要があると考えています。
ホテルオークラ東京(東京都港区)代表取締役専務 兼 The Okura Tokyo 総支配人 髙栁健二氏(以下、高柳) 当社では、従業員の声を拾うアンケートを毎年行っています。それに目を通していくと、やはり給与に関する声がもっとも多く寄せられており、切実な問題だと感じます。
そのため、ここ1年でできる範囲の報酬見直しを少しずつ進めています。一番手をつけやすいのが手当に関する待遇面で、ソムリエ、調理師など、様々なオペレーションスタッフの専門的な資格に対して資格手当の支給を始めました。また、労働負荷の高い時間帯の勤務である泊まり番のスタッフには、深夜手当にプラスアルファした手当も出しました。一定の効果があったと感じています。
全体的な待遇改善を進めながら、評価制度を見直して、最終的には長期的な報酬の体系を変えなければなりません。
労働環境改善~DX活用と勤務時間の見直しを

日本旅館協会 会長
大西 雅之 氏
大西 地方観光地の生活環境は、都会に比べて恵まれているとは言えません。娯楽や社会サービスも劣っています。しかし、都会にない自然の恵みも多々あります。この環境を楽しみながら仕事に従事できる働き方を提供するという意味で、当社では登山クラブや釣りクラブ、ゴルフクラブなど、業務以外の支援をしています。
近年はDXもかなり浸透し、接客現場では自動チェックイン機の導入から精算までの一元化が効果を上げています。レストランでは配膳、清掃ロボなどを導入しました。こちらは経験が増すにつれて効果が大きくなってきていると感じています。
また、管理部門でもITシステムの専属部署にSEを配置し、予約管理や経理システムなど、様々な業務にRPAを導入しています。データの集計分析など、ルーティンの業務を自動化することによって、効率化だけでなく単純作業からの解放による仕事の充実感向上に役立っています。
高柳 福岡での事例を紹介いたします。私が着任した2012年当時、日航グループだった旧JALホテルのチェーン・オペレーションをみて、オークラより非常に進んでいると実感しました。
従業員のモチベーションについては、たとえば『GoodJob制度』という表彰制度が定着していました。お互いに褒め合い、多く褒められた者が月間、年間で表彰される仕組みです。
チームを対象にした表彰では、QC(品質管理活動)についてサークルを設立し、取り組んだ内容を発表し表彰します。いずれもチェーンホテルオペレーションでは非常に有用な施策であると思います。
コロナ禍で中断しましたが、2016年に熊本の震災があり、会社として復興支援を名目に、近くのホテルや旅館に宿泊する場合の資金補助を支給していました。300人ほどのスタッフのうち6割が参加し、福利厚生として秀逸な取り組みだったと考えています。
陰山 当社は旗艦店のリーガロイヤルホテル大阪の大改装をしました。1030室の客室、10店舗の直営店、大規模宴会場があり、これまでの改装はお客様と接するところが中心でした。今回は従業員スペースの改装にも着手しました。食堂、カフェテリア、従業員休憩室、仮眠室、更衣室などを一新したのです。
また『健康経営宣言』を標榜して、3年ほど前から喫煙率の減少にも取り組んでいます。従業員のみなさんと時間をかけて相談しながら、従業員喫煙室の廃止に踏み切りました。結論として喫煙率を半分程度に減らすことができました。同時に健康相談室の一部に「がん相談室」を作りました。がん治療と勤務の両立についての従業員の悩みを受け止め、少しずつ相談が来るようになっています。
システムのDXも、徐々に取り組んでいます。財務諸表の作成を効率化するシステムを導入しました。AIを搭載したサービスレベルマネジメントシステム(ITサービスの品質・成果を、提供者と利用者が定期的・定量的に評価し、コストやニーズに最適なサービスを維持する仕組み)を2種類ほど採用して、今年から稼働させたいと考えています。
さらに業務工程では、例えば調理の「早朝勤務のみ」、宿泊の「深夜勤務のみ」といった働き方について見直します。サービス部では、宴会場には出ないものの、調理場との動線をカバーする担当者をアルバイトにするなどの選択も含め、様々な業務工程の見直しを進めています。
成功、失敗に関わらず、諸策に取り組んでいる姿勢を見せることが大事なのではないかと思っています。経営陣が従業員の方々の問題意識を理解していると知ってもらうことがポイントだと思います。
人材開発~『使う』でなく『育てる』環境づくり

代表取締役専務
兼 The Okura Tokyo 総支配人
髙栁健二氏
高柳 当社のホテル従業員にしめる外国人比率は5%に及びません。外国人スタッフを増やしていく必要はありますが、言語の課題は避けては通れません。
幸い当社のホテルグループは海外にも事業所があるので、そちらに人材を派遣して研修するチャンスはあります。今後は研修として20代のスタッフを常時派遣する制度を作っていきたいと考えています。
20代で海外での経験を積むことは、ホテルマンとして非常に大きな武器になるはずです。人材育成として若者に体験の場を用意するのも、海外にネットワークを持つホテルとしての責務だと思っています」
陰山 コロナ禍を経て、観光業界は就職希望者の親御さんや学校の先生からは避けるべき対象として捉えられている傾向があります。本来は人が好き、接客が好きな人が集まるやりがいのある職場ですが、不安定でキツイ職場だという見方がされているようです。
ホテル協会では、若い人たちへのアピールとして6点の短い漫画を作ってネット広告で流すなど、業界としての施策を試しています。
人材開発についても、昇進に意欲のある若い人がいる一方で、接客が好きでお客様とのホスピタリティに喜びを感じていたいという人もいます。そこを把握して、何がなんでも勉強させるという姿勢を一旦払拭する必要もありそうです。昇進に興味がない人には、定年を延ばすなど安心して働けるようなセーフティネットを作ることも検討しなければなりません。
一方で、若い人たちのやる気をすくい上げる制度も必要です。資格取得やコンテストへの出場、企業研修に積極的な人には、インセンティブを与える仕組み作りが大事になってきます。
大西 当社の取り組みでは、2007年から『敦賀観光人材養成講座』をスタートしており、夏冬の年2回、各2週間の合宿型の研修をしています。これまで17年間で32期600名を超える卒業生を送り出しました。
外部講師の他に、私も含め当社の役員や幹部が講師を務めます。観光業界に入ってきて、こんなはずじゃなかった、というミスマッチを防ぎたいと始めたものです。
欧米のホテル学校ではキャンパス内に自前のホテルを持っていて、座学と実学を同時に学べる環境がありますが、日本ではインターンシップぐらいしかありません。日本においても大学と宿泊業界が連携して、同じような環境を整えるべきと考えています。
昨年は、宿泊研修施設として多目的に活用できるコミュニケーション型宿泊施設『阿寒terrace』を完成させました。若手社員と街の若者の交流の場、外国人スタッフ同士の交流の場を作りたいという若手からの発案で開業しました。現在は大学のサマースクールにも利用いただいています。
人事評価も刷新しました。これまでの複雑で差異の見えづらいものから、基本3項目、成績・能力・情意に絞り、より直感的な評価ができるように改めました。
また上司からの指摘や褒め言葉を可視化して意欲の向上に繋げていく改善も進めています。Googleホームからスマホを利用して、部下からも自分の上司の評価や会社への意見提言を電子記載できるようにしました。上司の総合評価、職場内労働環境の整備などに反映させていく予定です。
『使う』から『育てる』ための教育としては、社内外の講師が自分の失敗談などを語る研修を増やしていきます。教わる方はもちろん、教える方にも学びがあるので、相乗効果があります。
外国人材についても真剣な議論が必要です。当社では外国人従業員が19%を超えています。それだけ人材確保が難しいわけですが、今後のインバウンド需要を考えれば武器にもなっていきます。
今後は外国人材のキャリア体制をどう作っていくかが課題となります。日本人社員と外国人社員のモチベーションはかなり違いがあり、その違いを把握して、人材を有効活用しなければなりません。
これから観光業を目指そうとする若者たちにも、いま頑張っている社員たちにも夢のある業界を取り戻したいと思います。旅館協会では、そのための具体的な目標とロードマップを描いていく所存です。