飲食店が人手不足の理由
各業界で人手不足が問題視されているが、それは飲食店においても例外ではない。帝国データバンクの資料によると、東京都に本店をおく企業に調査を行なった結果、正社員の人手不足割合は55.3%、非正社員だと31.2%というデータがある。
また業種別で見ると、飲食店で正社員が不足している割合は62.5%と上位9業種に、非正社員だと87.5%と上位2業種に入っているのだ。特に飲食店はパートやアルバイトなどの雇用が多く、非正社員の人材確保に難航していることが伺える。
参考:帝国データバンク「⼈⼿不⾜に対する企業の動向調査(東京都)」
飲食業界では、人材採用を行なってもすぐに辞めてしまうことが人手不足の大きな原因である。厚生労働省の資料では、令和2年の新卒者が就職後3年以内に離職した割合を見ると、高卒では「宿泊業、飲食サービス業」がトップで62.6%、大卒においても「宿泊業、飲食サービス業」がトップで51.4%という結果だ。
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」
新たな人材を雇用してもすぐに辞めてしまっては、採用や教育にかけたコスト分がマイナスとなってしまう。飲食店が人手不足に陥っている要因を、大きく分けて3つ挙げられる。
業務負担が大きい
飲食店は基本的に休みが不規則であり、24時間営業や深夜営業、開店前の仕込みや終業後の片付けなど、どうしても長時間労働になりやすい業種のため、従業員への業務負担が大きくなってしまう。
また人員が少なければ少ないほど休憩を取りづらく、状況次第ではそのまま働き続けなければならないこともありえる。肉体的にも精神的にも負担がかかることから、なかなか人材が定着しにくい課題が挙げられる。
休日が少ない
慢性的な人手不足に陥っている飲食店では、そもそも少数の従業員でシフトを組まなければならないため、休日が少ないことがある。少人数でお店を回している場合、急な欠勤に厳しい目を向けられることもあり、余計に休みが取りづらい状況となっている。
特に飲食店は、他の業種と比べて休みが少ない傾向だ。農林水産省の資料では、全産業の年間休日が約121日なのに対し、飲食・娯楽は113日という結果になっている。
参考:農林水産省「外食・中食産業における働き方の現状と課題について」
また従業員の欠勤などイレギュラーな対応に追われ、本来休みだったはずのスタッフが休日出勤をしなければならないケースもあるだろう。飲食店では、こうした急な予定でシフトが崩れることも考えられる。
責任が強くのしかかる
飲食店は、基本的に多くの従業員がパートやアルバイトで構成されており、各店舗に配属される正社員は1人しかいないということもある。そのため、店舗責任者である店長1人に責任が重くのしかかる。
加えて正社員が1人だと、どうしても店舗管理者がいない時間が発生してしまい、その間は時間帯責任者などをパートやアルバイトスタッフに任せる必要が出てくる。正社員だけでなく、パートやアルバイトのスタッフにまでも責任が強くのしかかることもあるのだ。
強い責任感はモチベーション向上にもなるが、一方でミスやクレームなどが発生すると大きなストレスや負担になってしまう。
人手不足を解消する2つの対策
飲食店の人手不足を解消するには、どのような方法があるのだろうか。ここでは主に2つの観点から行う対策について解説していく。
人材採用の前に、待遇や育成の見直しを図る
そもそも離職率の高い飲食店では、労働環境や待遇の改善を図ることで従業員が離れていくことを抑制する必要がある。具体的には、ES(従業員満足度)を向上させることが重要だ。
見直すポイントとしては、従業員が「仕事にやりがいを感じているか」「現在の処遇に満足しているか」「人間関係は上手くいっているか」「職場での悩みはないか」などが挙げられる。これらの項目の中から、満足度の低いものを優先的に改善していくことが必要だ。
また従業員の業務負担やストレス軽減を目的とした制度を作ることも大切だ。適切な休憩時間を設けることや、休みが取りやすいシフト作りなどを行うことが該当する。これにより従業員のモチベーションが高まれば、業務の生産性アップや離職率の低下といった様々なメリットとなる。
DXやデジタルツールの推進
限られた人材で効率的に業務を遂行するためには、事務作業をデジタル化して手間を減らすことが近道となる。そのために、DXの推進やデジタルツールの導入などを検討して見るのも1つの手段だ。
例えば、受発注システムや店舗オペレーション管理ツールなどを活用すれば発注に関わる業務の効率化や、リアルタイムでのタスク管理や作業マニュアルの確認などが簡単に行える。ツールを導入することで社員への属人化も減らすことができるため、ぜひとも活用してほしい。
人材採用、育成で人手不足を対策する方法5選
飲食店で人手不足という課題を解決するために、具体的に何をすればいいのかを考える際に活用できる人材採用や育成に関するノウハウをまとめてみた。資料は無料でダウンロードができるため、気になるものは参考にしてみよう。
新卒採用・教育を見直す

「飲食店の新卒採用と
教育の注意点」
新卒の採用や教育では、主に「Z世代」の若者に焦点を当てた採用や教育が必要になる。なぜなら、10代~20代前半の特徴や価値観を理解することで、戦力となる人材確保や離職率の低下に繋がるからだ。
例えば、Z世代の就職観は「楽しく働ける職場」や「プライベートの時間を取れる」といった人が多く、会社や仕事とは良い距離感を保ちつつプライベートも大切にしたいという考えを持っている。
またこの世代の特徴としては、テレビや新聞などのマスメディア離れが進み、SNSやYouTubeといったソーシャルメディアを利用していることが多い。X(旧ツイッター)やWebサイトでの情報収集が当たり前なため、就職を考えている企業の情報もそういった媒体を利用する可能性が高い。
だからこそ、ネットの口コミや評判などから自店舗の客観的なイメージを掴み、求職者にとって魅力的な企業に見えているかなどの判断が必要だ。実際に働くアルバイトスタッフなどに意見を求めてみるのもありだろう。
新卒採用についてより詳しく知りたい方はこちら
人材採用と組織づくりを見直す
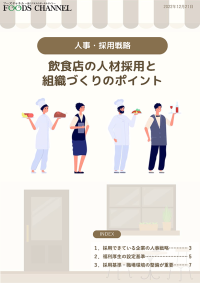
「飲食店の人材採用と
組織づくりのポイント」
飲食店の人手不足を解消するには、人材採用や組織づくりの面で改善を図ることが必要だ。例えば競合他社と比べて、自社の募集は求職者が集まるような魅力的な条件を提示できているかを見直してみてほしい。
注目すべきポイントは、働きやすい労働環境やキャリアアップにつながる職場であることだ。具体的な要件としては、「給料や休みの多さ」「残業時間の少なさ」「福利厚生の充実」「昇給や賞与の詳細」などが挙げられる。
「毎年どの程度給料が上がるのか」「どうすれば昇格できるのか」などという求職者の疑問や不安を1つ1つ解消することで、飲食業界を志す人が増える可能性が高まるからだ。もちろん魅力的な労働環境を整えるには、適切な評価制度や新たな福利厚生の提案などの下地づくりも必要不可欠となる。
人材採用と組織づくりについてより詳しく知りたい方はこちら
組織改革をし、“仕組み”で見直す

「人手不足を“仕組み”で解決!
飲食店の組織改革術」
人口の減少や少子高齢化などの影響により、今後の日本では働き手の減少がより顕著になっていく。そんな情勢の中では、1人の従業員が辞めただけでも貴重な戦力を失うことになる。
ではどんな職場環境であれば、従業員は辞めないのだろうか。例えばサービス業で働く人に聞いた「辞めない理由を調査したアンケート結果」では、「良好な人間関係」「充実した教育制度」「明確な評価制度」「よい労働条件と環境」などが挙げられている。
また年間離職率が20%以下の企業を調査した「人が辞めない会社の共通点」では、役職やキャリアに応じた人事評価制度や教育プログラムが深く関わっている。
これらの調査から導き出されたのが、株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパンの有本氏が提唱する、『グローイング・サイクル』だ。具体的には、「基準を示す」「教える」「要求する」「評価する」という4ステップで構成されており、人材の定着に必要なアクションが集約されている。
採用や求人の前段階としてまずは人材が定着する仕組みを作り、組織改革に取り組むことが人手不足への有効な対策となるだろう。
組織改革術についてより詳しく知りたい方はこちら
SVに必要なスキルと役割を整理する
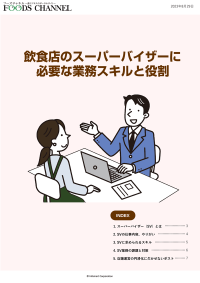
「飲食店のスーパーバイザーに
必要な業務スキルと役割」
多店舗展開する飲食店では、様々な店舗の管理や監督業務を行うSV(スーパーバイザー)の存在は欠かせない。どのようなスキルが求められるのか、本来どのような役割を果たすのかをしっかりと理解することで、優秀な人材確保・育成につながるだろう。
例えば、SVの主な役割は担当店舗の業績を伸ばすことだ。目的を達成するためには、店舗の売上状況の確認在庫・発注のチェックなどを行い適切な改善を促す。提供メニューや接客などに問題があれば、従業員への指導を実施する必要もある。また、本部からの方針を各店舗へ伝え、橋渡し的な役割も果たす。
飲食店において中長期的に店舗数を増やしていくためには、SVという重要なポジションに就く従業員の確保や育成は必要不可欠だ。新規出店する際に「管理者がいない」という事態を防ぐためにも、SV候補となる人材の選出などは十分に検討しておこう。
SVに必要なスキルと役割についてより詳しく知りたい方はこちら
パワハラ防止法を理解する
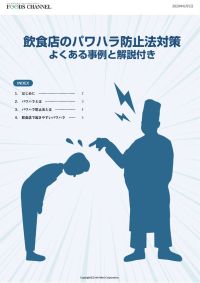
「飲食店のパワハラ防止法対策
良くある事例と解説付き」
飲食店では見習いとして働く従業員に厳しく指導する”というのは昔の話で、2024年現在では行き過ぎた指導や言動などが問題になることも多い。2020年6月からはパワハラ防止法が施行されており、違反した事業者には行政指導が行われる。
そもそもパワハラという行為は、従業員が離職する大きな理由の1つでもある。そのため、飲食店の人手不足解消にはこのパワハラに対する認識を改めなければならない。例えば、相手を叩くなどの身体的な行動はもちろんのこと、脅迫や侮辱といった言葉による暴力、仲間はずれや無視なども該当する恐れがある。
また皿を割った際に罰金を科す、本人の能力とかけ離れた業務を行わせるなど、明らかに過大・過小な要求もパワハラになり得る。しかし一方で指導者側がパワハラに怯え、適切な教育ができないとサービス品質の低下などを招いてしまう。
そして事業者は、どこまでが指導で何がパワハラになるのかといった線引きを行い、従業員へ正しく周知・教育することが重要になるだろう。
パワハラ防止法やパワハラ行為についてより詳しく知りたい方はこちら
労働環境や社内制度を見直した組織改革で人手不足を解消
飲食店の人手不足は、給料や待遇、厳しい労働環境などが主な原因として挙げられる。
まずは自社に何が足りないのか、従業員がどんな不満を抱えやすいのかを把握することが大切だ。その上で採用に力を入れるのか、社内制度を充実させるのかといった方向性を見極めることが必要になる。
しかし、職場環境の改善や人材育成などには時間もコストもかかる。人手不足の課題を解決できる飲食店づくりのために、今回のノウハウを活用しよう。












