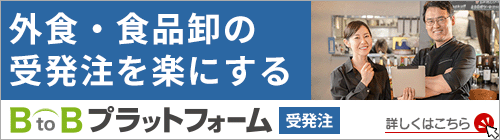リクエスト株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役 甲畑智康)は、企業文化と人的資本経営の未来に向けた提言書『効率の先にある「選ばれる企業」への転換』を2025年4月16日に公開しました。
効率は進んだ。けれど、何かが足りない。現場のスピードは上がり、成果も数字で見えるようになった。でもいま、「誰の役に立っているのか分からない」「やりがいが感じられない」という声が、確かに聞こえてきています。これは、働き方の“進化”の裏で、「行動の意味」が置き去りにされつつあるという兆しではないでしょうか。私たちは今、「効率」だけでなく、「信頼を生む行動」そのものを見直し、再設計する岐路に立っています。
本提言書は、「効率の最適化」が飽和した社会において、“信頼され、選ばれる企業”が何を守り、何を継承していくべきかを、価値観・制度・育成・AI支援の観点から、構造的かつ感情知的に整理した提言です。この取り組みは、私たちが提唱する組織行動科学(R)の最新知見と実践に基づいています。

提言書 目次
- 創業時にあった“効果志向の価値観”はなぜ失われたか?- 「行動の質」が削られた結果、何が起きているか?
- 効率化では差別化できない時代に入った
- 外部の仕組み導入と組織の“空洞化”リスク
- 「行動の質」を決めるのは、スキルではなく価値観
- 価値観の違いがもたらす事業・組織・人材への影響
- 意味ある行動が埋もれない“職務設計”とは?
- 「行動の意味」を再定義する17の経験ステップ
- 価値観を育てる組織が、選ばれる企業になる
- 生成AIが支える、意味ある行動の再構成とリーダー育成
- 最後に:問うべきは「何を削り、何を守るか」
- 提言書の使い方|実践編
- あとがき
- 参考1.:選ばれる企業への転換に向けた「10の問い」
- 参考2.:価値観リスト
- 参考3.:巻末用語解説
- 参考4.:思考の訓練ガイド
- 参考5.:立場別「この視点で読むと良い」読解ガイド
- 参考6.:弊社について
- 補足資料:価値観を職務評価・人事制度に接続するための設計案

▼ 提言書 無料ダウンロード
d68315-118-19f62a36cf7602cca5eb4b6f6b1e0f44.pdf50ページ(最終更新日:2025年4月21日)
※ リクエスト株式会社は、「Behave:より善くを目的に」を掲げ、国内336,000人の組織で働く人たちの行動データに基づいた組織行動科学(R)を中核ブランドとし、人間の行動と思考を研究開発する5つの機関が連携。これまで930社以上の人的資本開発を支援してきました。
https://www.requestgroup.jp/

【提言書:サマリー】
1. 現状の組織の問題(組織行動科学(R)より)
効率の限界と、「意味のある行動」が失われつつある現場のいま:多くの企業では、業務スピード・正確性・コスト削減といった「効率化」がすでに一定の水準に達し、短期的な成果の最大化には大きく貢献してきました。これは、少子高齢化・人手不足・時間制約といった社会的制約への合理的な適応でもあり、経営判断として正当なものであったといえます。
しかし今、その“成果の裏側”で、見過ごせない兆しが現れ始めています。それは、特に自ら考え、全体構造を見て動けるごく一部(およそ10%程度)の社員層から発せられる、静かだが鋭い声です。
- 「誰の役に立っているのかがわからない」
- 「成果は出ているが、やりがいを感じない」
- 「対応は早いけれど、心が通わないと顧客に言われた」
こうした声は、今はまだマイノリティかもしれません。けれどもこの層は、組織において「価値観と行動のズレ」に最も早く気づける存在。彼彼女らが感じているのは、単なる不満や疲れではありません。そこには、言葉になりきらない違和感と共に、組織の未来に向けた“問い”が込められています。
たとえば、
- 顧客対応のスピードは上がったが、「冷たくなった」と言われるようになった
- 数字は伸びているのに、離職率は下がらず、愛着を語る声が減ってきた
- KPIは達成されていても、社内の関係性に温度が感じられない
こうした現象は、単発の出来事ではなく、“行動の意味”が失われつつある兆候といえるでしょう。そしてこの意味の喪失は、放っておけばやがて組織全体に波及し、取引先や顧客との信頼、社内メンバーの誇り、そして文化としての企業らしさを徐々に損なっていきます。
問い:いま、自分たちの組織において「見過ごされている違和感」はないか? それは“行動の意味”の喪失に起因していないか?
【補足:違和感の正体 ―「ズレ」を捉える力】
違和感とは、ただの主観や不満ではありません。実はそれは、「こうあるべきだ」という善き状態のイメージと、実際の経験や観察から得た現実の事実との“差”を感知する力です。
ここで重要なのは、「こうあるべきだ」というその“善き状態”が、単なる個人の理想や感覚ではなく、その企業が取引先や顧客との関係の中で培ってきた“独自の価値観”に根ざしているという点です。
たとえば、
- 顧客が安心できる対応を大切にしてきた企業であれば、「成果は出ているが、何か冷たくなった気がする」という違和感が生まれる。
- 課題の本質に寄り添う提案を心がけてきた現場であれば、「最近、言われたことしかしていない気がする」という声が上がる。
こうした違和感は、組織に受け継がれてきた関係性の価値観と、今起きている現実との“ズレ”を敏感に察知する働きに他なりません。つまり、違和感を覚える人は、企業らしさを最も深く知る存在でもある。その違和感を放置せず、問いとして言語化していくことが、組織にとっての“未来の軌道修正”となります。違和感とは、未来からの問いかけである。そしてそれは、組織の“価値の原点”に触れている。
問い:いま、現場に広がる“違和感”を見過ごしていないか?
2. 意味ある行動とは何か?それは“より善くなる関係”を生む工夫
“意味ある行動”とは、単に丁寧で親切なふるまいを指すのではありません。それは、顧客・取引先・社内メンバーにとって、「より善い状態」への一歩を生み出す工夫と判断のことです。たとえば、- 工程の混乱を察知し、納品タイミングを調整する
- 顧客の曖昧な要望を読み解き、背景にある本質的な課題を提案に落とし込む
- チームメンバーの詰まりに気づき、仕事の手を止めて声をかける
これらは、マニュアルやルールでは指示できません。しかし、いずれも“誰かの安心や成功を支える行動”として、確実に信頼を築いていきます。
その背後には、「効率」だけでなく、「効果を生む価値観」が根づいています。「何を早く・正確にやるか」ではなく、「誰に・どんな関係で価値を届けるか」という視点が、行動の質を決定づけているのです。

問い:自分たちの行動は、「誰に・どんな関係で価値を届けているのか」という視点で見直せているだろうか?
3. なぜ、“意味ある行動”は取引の維持・拡大につながるのか?
取引が続き、広がっていく企業には、数値では測れない共通の評価があります。- 「こちらの状況をよく理解してくれている」
- 「困ったときに、まず相談したくなる」
- 「提案が一歩先を読んでいて助かる」
これらの言葉は、単なる親切さや対応スピードを指しているのではありません。その背後には、“こちらの立場や構造、関係性まで踏まえて動いてくれている”という安心感と信頼があります。
たとえば、
- 「こちらの状況をよく理解してくれている」とは、目の前の依頼だけでなく、その背景にある現場の事情や工程全体の流れ(バリューチェーン)をくみ取りながら、最適な関わり方を選んでくれているということ。
- 「困ったときに、まず相談したくなる」とは、こちらの意図や制約をふまえつつ、表面的な応答ではなく、“どう関われば価値が出せるか”を一緒に考えてくれる存在であること。
- 「提案が一歩先を読んでいて助かる」とは、与えられた情報だけでなく、事実の奥にある“構造のズレ”や“関係性の変化”まで想像し、先回りして対応してくれていることへの信頼です。

このように、“意味ある行動”は、単なる作業や礼儀ではなく、相手の状況・背景・人間関係を含む全体文脈への想像と接続から生まれるのです。そして、それが積み重なることで、
- 値引きではなく“信頼”で選ばれるようになる
- 「相みつによる比較対象」ではなく「共働」の対象となる
- 「この人・この会社とならやっていける」という関係性の資産が築かれる
すなわち、“意味ある行動”とは、価格競争を超えて、継続的な取引と紹介を生み出す“無形の競争力”でもあるのです。
問い:自社が「信頼されて選ばれている」としたら、それはどんな“関わりの質”が評価されているからか?
4. どうすれば、“意味ある行動”を再現できるのか?
このような行動は、感覚や性格に依存するものではありません。実際には、誰もが通る「内面的な変化のプロセス=価値観の成長ステップ」を経て、意味ある行動を獲得していきます。主体性と信頼を育てる「価値観の成長ステップ」
(行動アンラーニング(R) :「既存の思考や行動の前提を問い直し、意味を再構築する成長プロセス」)
- 違和感に気づく:「このままでいいのか?」と自分の行動をふり返る
- 内省する:自分の行動が誰にどう影響しているのかを考える
- 相手を想像し、対話する:相手の背景(バリューチェーン)に目を向け、対話を重ねる
- 意味を実感する:相手の反応を通じて「やってよかった」という手応えを得る
- 行動が波及する:周囲の行動にも影響を与え、信頼の循環が生まれる
- 文化になる:行動の意味が言語化され、共有・継承されていく
このステップは、個人の気づきを起点に、チーム・組織へと波及していく流れを生み出します。そして、それが再現可能な仕組みとして根づいた時、組織の文化は「行動の質」に支えられたものへと進化する。

5. 再現可能にする鍵=生成AIの活用
属人的な「良い動き」を組織に定着させるには、行動の背景・構造・意味を整理し、言語化・共有するプロセスが欠かせません。その知的補助役として、私たちは生成AI:人的資本開発アシスタント(R)「育成・評価・継承支援を行う知的補助者として機能する仕組」を活用しています。生成AIの主な役割:
- 構造化の補助者:実践経験を「事実・背景・意味」に分解・整理
- 多視点評価の分析者:目的・関係性・変化・再現性など多角的に評価
- 次の行動のヒント提供者:気づきを次の行動につなげる“問い”を生み出す
生成AIは単なる効率化ツールではありません。行動の意味を構造的にひもとき、再現性のある“学び”として可視化・共有する存在です。これにより、個人の経験が組織の知へと翻訳され、文化として定着していきます。

さらに、生成AIは単なる記録や整理の補助者にとどまらず、その場の対話を深める“共創ファシリテーター”としての役割を担いはじめています。たとえば、会議や1on1の対話中に、相手の発言の背後にある価値観や構造をリアルタイムで抽出・提示し、その場にいる双方が「なぜこの行動を取ったのか」「本当に信頼を生む関係とは何か」を言語化しながら深め合う。
生成AIは、もはや“過去の記録”を整理するだけの存在ではありません。「問いを共につくるパートナー」として、思考の場・関係性の場にリアルタイムで入り込み、意味の再構成と信頼の醸成を支える共創者へと進化しつつあります。
このようなAIの活用は、既存の研修や評価面談、対話型会議においてすでに導入が始まっています。たとえば「経験の棚卸し」や「行動の意味づけ対話」において、過去の事例から“信頼の兆し”を抽出し、メンバーと共に意味を整理・再定義する場づくりが実現しつつあります。
6. 経営層の皆様へ ― 次世代に残すべき行動とは?
ここまで見てきたように、「意味ある行動」は、成果だけでなく信頼も生み出す、企業にとって最も本質的な価値創出の源泉です。だからこそ、今こそ問い直すべきです:- 御社にとって、“削ってはいけない行動”とは何でしょうか?
- その行動は、誰にとって、どんな“より善い変化”を生んでいますか?
- それを再現可能にし、組織の仕組みとしてどのように継承していきますか?
経営とは、短期成果を最大化する「仕組み」を整える営みであると同時に、長期的な信頼を育てる「行動」を選び取り、守り抜く意思決定の連続でもあります。いま私たちが守るべきなのは、誰かがより善くなるために、自ら考えて動いたその一歩”なのではないでしょうか。
用語解説
■ 行動アンラーニング(R)これまでの思考や行動の前提を一度手放し、現場での経験を通じて「意味」を再構成していく学習・変化のプロセス。既存の“正しさ”にとらわれず、違和感や内省、対話を通じて、主体的な行動と信頼関係を再構築していく道筋を指す。→ 変化の時代において、過去の成功パターンを手放し、“信頼される行動”に進化するための必須プロセスである。
■ 組織行動科学(R)
人と組織の間にある行動・心理・関係性の変化を科学的に捉える学問領域。行動の背後にある「構造・関係・文脈」を分析し、持続的な組織の進化を支援する設計思想でもある。→ “表面的な行動の良し悪し”ではなく、その背景にある構造的要因まで見抜き、組織全体の質を高める視点を提供する。
■ 意味ある行動
顧客・取引先・社内メンバーにとって、「より善くなる」ためのきっかけを生み出す行動。単なる業務の遂行ではなく、背景や関係性を想像し、相手の状況に応じた創意ある関わりを含む。→ 自らが行った行動が相手の変化や成長を支え、やがて信頼を生み、その信頼が継続的な共働や事業成果につながっていく。“誰の、何を善くしたのか”という視点こそが、信頼・成果・文化の連鎖を生む起点となる。
■ 人的資本開発アシスタント(R)
生成AI(GPTなど)を活用し、リーダーの育成・実践経験の内省・行動の意味づけ・知の継承を支援する仕組み。人間の思考を補い、意味の再構築と対話の質を高める“知的共創パートナー”として機能する。→ 育成や評価において“何を大切にして動いたか”を言語化し、組織全体での学びと継承を可能にする。
■ 条件設定思考(R)
思考や対話を進める前に、「目的」「前提」「問いの設計」などの条件を明確にし、対話の質や行動の意味づけを高めていくプロセスを指す。生成AIとの対話やリーダー育成の場面において、思考の深まりと再構成を可能にする前提づくりの力である。→ 変化の多い時代において、「正解の探求」よりも「意味の再定義」が求められる中、対話や判断の起点となる不可欠なリーダーシップスキルである。

【提言書無料ダウンロード】
『効率の先にある「選ばれる企業」への転換』~ 信頼を生む行動の文化化 × 生成AIによる知の継承 ~
▼ この資料で得られること
- 行動の「質」が成果と信頼の両立を可能にする構造とは?
- 行動が文化になる6ステップと再現のプロセス
- 生成AIが人的資本開発アシスタント(R)として担う支援とは?
- 経営層への問い:「削ってはいけない行動」とは何か?
▼ こんな方におすすめ
- 人的資本経営を“言語と仕組み”で支えたい経営・人事・現場責任者
- 生成AIを育成・評価に本質的に活かしたいリーダー
- 「組織文化はどう育つか?」を探求している方
▼ 提言書ダウンロード:
50ページ(最終更新日:2025年4月21日)d68315-118-92fff5e4bce2f965e21d204b92ccaf53.pdf
提言書 目次
- 創業時にあった“効果志向の価値観”はなぜ失われたか?- 「行動の質」が削られた結果、何が起きているか?
- 効率化では差別化できない時代に入った
- 外部の仕組み導入と組織の“空洞化”リスク
- 「行動の質」を決めるのは、スキルではなく価値観
- 価値観の違いがもたらす事業・組織・人材への影響
- 意味ある行動が埋もれない“職務設計”とは?
- 「行動の意味」を再定義する17の経験ステップ
- 価値観を育てる組織が、選ばれる企業になる
- 生成AIが支える、意味ある行動の再構成とリーダー育成
- 最後に:問うべきは「何を削り、何を守るか」
- 提言書の使い方|実践編
- あとがき
- 参考1.:選ばれる企業への転換に向けた「10の問い」
- 参考2.:価値観リスト
- 参考3.:巻末用語解説
- 参考4.:思考の訓練ガイド
- 参考5.:立場別「この視点で読むと良い」読解ガイド
- 参考6.:弊社について
- 補足資料:価値観を職務評価・人事制度に接続するための設計案
【本件に関するお問い合わせ】
リクエスト株式会社Human Capital Development XR HRD(R) Team
E-mail:request@requestgroup.jp

【会社概要】
社名:リクエスト株式会社
- 所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目4番8号 京王フレンテ新宿3丁目4F
- 代表者:代表取締役 甲畑智康
- 事業内容:組織開発・人材育成・AI活用支援 等
- ブランド基盤:組織行動科学(R)
- コーポレートサイト:https://requestgroup.jp/
- 代表プロフィール:https://requestgroup.jp/profile
- 会社案内ダウンロード:https://requestgroup.jp/download