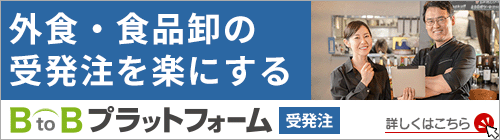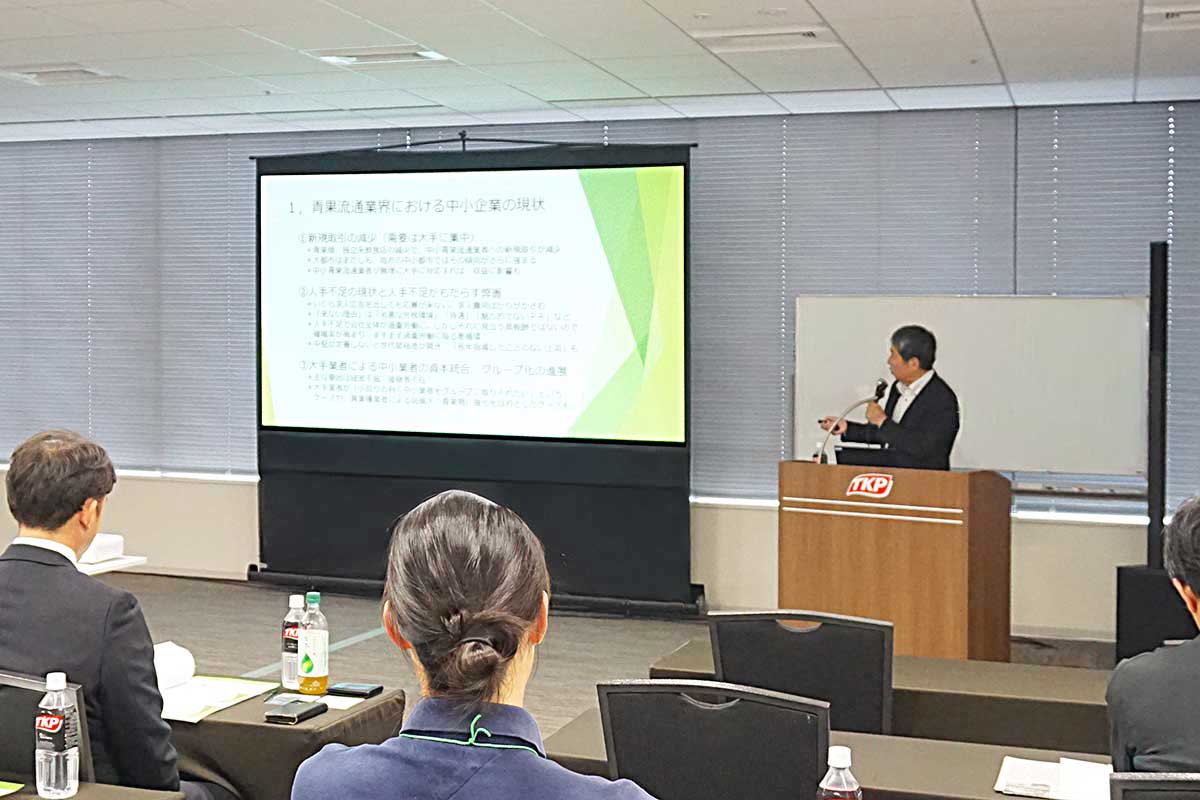出典:ながさきBLUEエコノミー
一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA:代表理事/会長 津賀 一宏 パナソニック ホールディングス株式会社 取締役会長)は、国内最大級のデジタルイノベーション総合展「CEATEC 2025」(主催:JEITA)において、海洋産業へのデジタル技術の活用や次世代に向けた人材育成の取り組みを発信する「海洋デジタル社会パビリオン」を展開することを発表しました。本パビリオンは、水中光技術にとどまらず、最先端のスマート水産・養殖、環境モニタリング、再生可能エネルギー、水中ロボット等、海洋ビジネスの最新動向を発信するもので、参画企業・団体を募集しています。詳細はCEATEC 2025の公式 Webサイトをご覧ください。
昨年のCEATEC 2024においては、水中光技術の活用を通じて海洋産業のデジタル化と海の見える化を図り、新市場の創出や社会課題の解決に向けて活動する「ALAN(Aqua Local Area Network)コンソーシアム」を中心として「海洋DXパビリオン」を展開、「デジタルが紡ぐ海の未来」をテーマに技術普及や市場創出に向けた情報発信を実施しました。
本年は、さらに規模と内容を拡充し、スマート水産・養殖の事業者も新たに加わります。身近な美味しい魚が食卓に上がるまでに、海洋で何が起きているのか、そして周辺のビジネスの可能性がどれだけ広がっているのか、海洋産業の未来を多角的に考える場を提供します。
パビリオンの各出展者等の詳細は、今後順次発表します。
<海洋デジタル社会パビリオンの概要>
■開催趣旨
海洋デジタルの最前線を体験し、新たなビジネス・人材を創出
デジタル技術の進化は、海洋産業の可能性を飛躍的に広げています。AI・IoT・ビッグデータの活用により、環境問題の解決、食料自給率の向上、エネルギー資源の開発など、多様な社会課題に対応できる新たなビジネスが生まれつつあり、また、こうした技術革新を支える次世代人材の育成も急務となっています。本パビリオンでは、Society 5.0の理念を基に、海洋産業にとどまらず、IT・エレクトロニクス・AI・ロボティクスなどの業界・業種の垣根を超えた共創を促し、海洋産業の新たなビジネスモデルを生み出す場を提供します。
- 最先端技術の展示・体験(水中光通信、スマート水産・養殖、水中ロボット等)
- 業界リーダーによるカンファレンス(最新技術・政策・市場動向を発信)
- 次世代人材との交流機会(出展者および関係者とのマッチング)
■参画関係者(産官学)からの応援メッセージ
産
- ALANコンソーシアム(水中ネットワークによる市場創出)- 一般社団法人日本水中ドローン協会(水中ドローン(ROV)の利活用推進)
- 株式会社アイエスイー(海の見える化とデータ活用による持続可能な海洋環境の実現)
- おさかなだお長崎(Local web3 lab.@渋谷)(DAOを通じた漁業コミュニティの支援の取り組み)
官
- 内閣府 総合海洋政策推進事務局(海洋政策や政府の取り組み)学
- 長崎大学(COI-NEXT 持続可能な養殖事業の実現を目指す産学連携プロジェクト「ながさきBLUEエコノミー」- 北海道大学(内閣府地方大学・地域産業創生交付金 魚介藻類養殖を核とした持続可能な水産・海洋都市の構築~地域カーボンニュートラルに~貢献する水産養殖の確立に向けて~「函館マリカルチャープロジェクト」)
- 琉球大学(COI-NEXT 資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点「Blue & Green Revolution」
(他にも複数企業・団体が参画を検討中)
■参画企業・団体募集中
本パビリオンは、展示やカンファレンスを通じて海洋産業の可能性を発信し、来場者に事業領域の拡大や企業価値向上のヒントを提供します。さらに、学生や新規事業担当者に対して、海洋分野を将来のキャリアの選択肢として提示する場となることを目指しています。
海洋デジタル社会に関連する以下の募集テーマに該当する企業・団体の皆様を幅広く募集しております。詳細は下記の参画ガイドをご覧ください。
CEATEC 2025 海洋デジタル社会パビリオン 参画ガイド
参考:昨年の開催実績・様子


■参画事業者(産官学)からの応援メッセージ
産

ALANコンソーシアム 代表
アクアジャスト株式会社 代表取締役CEO
島田 雄史 氏海洋のデジタル化は、環境保全や産業発展に向けた大きな可能性を秘めています。ALANコンソーシアムでは日本の強みを活かした水中光技術を通じて、通信・センシング技術の発展に取り組んでまいりました。その取り組みの一環として、2023年にALANコンソーシアム発のベンチャー企業として「アクアジャスト」を設立し、水中センサ・ロボットの開発・実装を進めています。本パビリオンが、多くの皆さまとともに最先端技術や産官学の連携を深め、新たな海洋ビジネスの創出につながることを願っております
(ALANコンソーシアム)
(アクアジャスト株式会社)

日本水中ドローン協会 代表
株式会社スペースワン代表取締役
小林 康宏 氏私たち日本水中ドローン協会は、水中ドローンの利活用を通じて、海洋産業の安全性や効率性の向上、そして持続可能な社会の実現に取り組んでいます。近年、海洋分野におけるデジタル技術の進化は目覚ましく、水中ドローンは調査・点検・教育など多様な現場で活用が広がっています。本パビリオンは、こうした最新技術の展示にとどまらず、産学官が連携し、海洋の未来を語り合う貴重な場です。若い世代が海洋に関心を持ち、キャリアの選択肢として志すきっかけにもなることを願っています。
(日本水中ドローン協会)
(株式会社スペースワン)

株式会社アイエスイー代表取締役
高橋 完 氏私たちは、IoT海洋モニタリングシステム「うみログ」を通じて、海の見える化とデータ活用による持続可能な海洋環境の実現を目指しています。漁業現場や沿岸地域のリアルな課題に寄り添いながら、海の今を“いつでも見られる・活かせる”形で届けることを目指して開発してきました。本パビリオンが、最先端技術の展示にとどまらず、多様な分野の知見と経験が交わる場となり、海洋の未来を共につくる仲間との出会いや、新たな連携・挑戦のきっかけとなることを期待しています。
(株式会社アイエスイー)

おさかなだお長崎(DAO)私たち「おさかなだお長崎」は、“長崎のうまいサカナの未来をつくる”というテーマのもと、日本全国から賛同するメンバーがオンラインで集まり、メンバーそれぞれの力を生かして楽しみながら活動するDAO(分散型自律組織)です。長崎の豊かなおさかな、海洋資源を知りメンバーが自律的に企画、提案、推進、共創する場となっており、長崎の多彩なサカナの発信、食イベントはもちろん、大学と連携した学会発表や中学校での探究学習など様々な活動が生まれています。その中でも昨年のCEATEC 2024『海洋DXパビリオン』では、ながさきBLUEエコノミー様と合同出展させていただき長崎の魅力、豊かさを多くの方へ発信し、思いを同じとする方々との交流が生まれる有意義な機会となりました。
今年は『海洋デジタル社会パビリオン』がさらに規模と内容を拡充すると伺い、大きな期待を寄せています。場所や業界の垣根を超えた共創が生まれるこの場が、日本の海洋産業と地方創生の新たな可能性を広げる契機となることを心より願っております。
(おさかなだお長崎(DAO))
官

内閣府
総合海洋政策推進事務局 参事官
金子 忠利 氏海洋におけるDX(Digital Transformation)は、海域で発生する自然災害の防災・減災、海洋産業における利用、包括的・持続的な海洋調査・観測を含めた科学的知見の充実等に不可欠です。DXの要はデータであり、データは新産業を生み出す基盤となり得るものです。まずは産学官で利用してみるという姿勢で、海洋に関するデータの共有・利活用を加速し、データ解析・分析手法の開発も行いながら、膨大な海洋データを用いたデータ駆動型研究を推進することで、付加価値をもった情報を基にしたイノベーションを創出することが重要です。今年のCEATEC海洋デジタル社会パビリオンにおいて、水産業を主テーマに産学官で海洋のDXに関する活発な議論が行われ、海洋産業の発展に繋がることを願っておりま
学

長崎大学
海洋未来イノベーション機構 教授
征矢野 清 氏
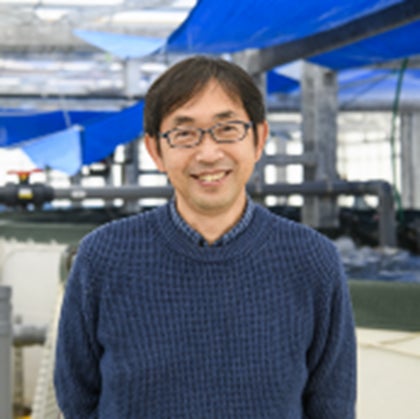
琉球大学
理学部 教授
竹村 明洋 氏

北海道大学
大学院水産科学研究院 教授
都木 靖彰 氏
「古来より、日本人は魚とは縁の深い暮らしをしてきました。その中で、美味しく健康的なわが国独自の食文化を作り上げてきたのです。今、世界も魚食を中心とした日本食に注目しています。
しかし、わが国の水産業は、資源量の減少や水産従事者の減少と高齢化、さらには、目まぐるしく変わる世界情勢の影響を受け、大きな転換期を迎えています。特に、とる漁業のみに依存するのではなく、養殖を中心とした水産業への転換が求められています。
私たち長崎大学、琉球大学、北海道大学は、JST(科学技術振興機構)のCOI-NEXT事業と内閣府の地方大学・地域産業創生交付金において、新たな養殖技術の開発と水産業とその関連産業に関わる全て人々の人材育成に本気で取り組んでいます。
これは、日本人が当たり前のように感じている「魚食」や「海と共生した暮らし」を持続的に守り、拡大するための取組みです。私たちは、海洋工学・デジタル技術を活用した生産者の省力化や生産効率のための研究に、AIやIoT、ビッグデータを活用することによってより、海洋産業の新たな可能性の創出を目指しています。
また、生物学的技術も合わせて導入することにより、環境保全型養殖による持続可能な資源利用の加速を進めています。私たちは、海洋エネルギー開発や水産技術革新、海洋環境モニタリングなどを通じて、海洋DXの推進と持続可能な社会の実現に貢献できることを確信しています。
本パビリオンは、海洋産業とデジタル技術の融合を体感できる場です。 多くの企業・研究機関の皆様と共に、海の未来を切り拓くイノベーション創出を目指していきたいと考えています。本イベントの成功を心より応援しています」
【本件の出展関係者からのお問合せ先】
海洋デジタル社会パビリオン 運営事務局(一般社団法人 電子情報技術産業協会内)
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル 4F
担当: 飯沼・白鳥
E-mail:oceandx@jeita.or.jp