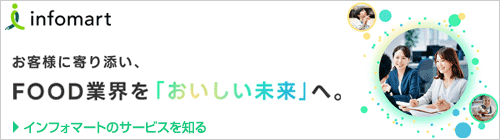カスハラ防止条例の成立背景
東京都のカスハラ防止条例は、顧客による不当なハラスメント行為から従業員を守り、働きやすい職場環境を整備することを目的としている。この条例成立の背景には、カスハラ問題の深刻化がある。
カスハラとは、顧客が従業員に対して不当な要求や暴言、暴力行為を行うことを指し、近年、社会問題として注目を集めている。特に、飲食業や宿泊業など、顧客対応が業務の中心となる業界では被害が多い。この問題により、従業員の離職率が高まり、事業運営への悪影響が懸念されている。こうした課題に対応するため、東京都は条例の制定に踏み切った。
カスハラが事業者に与える影響
カスハラは被害を受けた従業員だけでなく、事業者全体に次のような影響を及ぼす。
●従業員の離職率上昇
カスハラが繰り返される環境では従業員のモチベーションが低下し、職場への不信感が生まれる。この結果、サービス業では離職率が上昇し、人材不足が一層深刻化している。特に、飲食業界や宿泊業界は従業員の採用が難しいため、カスハラ問題は経営に直接的な打撃を与える。
●業務効率の低下
カスハラ対応には、多くの時間と労力が費やされる。対応が長引くことで他の業務や顧客対応が停滞し、結果的にサービス全体の効率が低下する。これにより、店舗や施設のイメージ低下、リピート率低下につながるリスクがある。
●法的トラブルへの発展
悪質なカスハラ行為がエスカレートした場合、トラブルが法的な問題に発展する可能性もある。例えば、従業員が暴力を受けた場合や、精神的ストレスから労災申請を行うケースが増えている。
東京都の条例制定に至る経緯
東京都はこうした状況を踏まえ、2024年10月にカスハラ防止条例を制定した。条例制定に至る要因の一つに、カスハラ問題に関する都内事業者からの声が挙げられる。特にサービス業を営む中小企業からは、以下のような要望が寄せられていた。
●顧客対応で悩む従業員を支える仕組みが必要だ。
●カスハラが発生した際の対応フローを明確にしてほしい。
●行政がサポートに関与し、全体的な意識改革を進めてほしい。
こうした要望を反映する形で、東京都は事業者が活用できるガイドラインを2024年12月に公開し、カスハラ防止条例を2025年4月に施行するとした。
カスハラ防止条例の内容とガイドラインが示す対策
東京都が策定したガイドラインは、従業員が業務中に直面するトラブルの具体例をもとにしている。カスハラの定義や事業者・顧客が果たすべき責務について解説する。
カスハラの定義
カスハラとは「顧客等が就業者に対して業務に関して行う暴言や暴力、不当な要求などの『著しい迷惑行為』であり、これによって就業環境が害される行為」と定義している。
(例)
●客が食事やサービスに対して、明らかに過剰で理不尽な要求を繰り返す。
●従業員に対して怒鳴り声をあげる、侮辱的な言葉を浴びせる。
●物を投げつける、身体的な暴力をふるうなどの行為を行う。
対象者の責務
ガイドラインでは、カスハラを従業員だけの問題とせず、顧客、従業員、事業者それぞれの責務を明確にしている。以下に、それぞれの役割を説明する。
| 顧客の責務 | 従業員の責務 | 事業者の責務 |
|---|---|---|
・あらゆる場において、カスハラを行ってはならない ・カスハラが起こる社会的背景、カスハラ行為、事業者への影響などに関心と理解を深める ・就業者と対等の立場であることを前提に、自らの言動に注意を払う ・カスハラ防止施策に協力する | ・カスハラの被害を受けた場合の対応などに理解を深める ・カスハラを未然に防ぐための積極的な行動をとる ・事業者が実施するカスハラ防止の取り組みに協力する | ・カスハラ対応方針、防止策、対応策を定めるなど、主体的かつ積極的に取り組む ・就業者がカスハラを受けた場合、速やかに安全を確保する ・カスハラが発生した際、行為者に止めるよう要請し、退去、出入り禁止、商品サービスの提供中止などの通告をする ・従業員にも取引先にカスハラをさせない措置を取る ・FC加盟店経営者やその従業員、派遣労働者など雇用関係がない場合でも、雇用関係がある就業者と同様に取り扱う ・カスハラ防止施策に協力する |
罰則の有無
東京都のカスハラ防止条例では、直接的な罰則規定は設けられていない。しかし、カスハラ行為が刑法や民法などの法令に抵触する場合は法的措置が取られる可能性がある。
(例)
●暴力行為
刑法208条の暴行罪や傷害罪に該当する。
●侮辱や名誉毀損
侮辱的な発言やSNSでの誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪となる場合がある。
●不当要求
繰り返しの不当な要求が業務妨害に当たる場合は、刑法234条の威力業務妨害罪となる。
事業者や従業員は、こうした法的手段を視野に入れ、必要に応じて警察や弁護士の協力を得ることが求められる。また、今後の条例改定により罰則規定が追加される可能性も指摘されている。
カスハラ発生時の対応策と事業者が取るべき行動
カスハラが発生した場合、事業者はトラブルがエスカレートする前に迅速かつ適切な対応が求められる。東京都のカスハラ防止ガイドラインでは、事業者が取るべき行動が明確に示されている。具体的な対応策を解説する。
初期対応~責任者による迅速な介入
カスハラが発生した際、まず重要なのは、現場の従業員が一人で問題を抱え込まないことだ。東京都のガイドラインでは、以下のような初期対応が推奨されている。
●責任者の対応を徹底する
責任者や管理職が迅速に現場に介入することで、従業員への負担を軽減できる。特に、トラブルが長引く、感情的な対立が発生した場合には、責任者の冷静な対応が状況の収束に繋がる。従業員には、異常な状況を感じたらすぐに責任者を呼ぶよう指導しておくことが重要だ。
●当事者の分離
カスハラの被害を受けている従業員を現場から離し、休息を取らせる。また、カスハラを行う客には、別の責任者が冷静かつ毅然とした態度で対応を行う。これにより、当事者同士の感情的な衝突を防ぎ、事態を沈静化させることができる。
責任者が迅速かつ適切に介入することで、現場の混乱を抑え、従業員が安心して働ける環境を守ることができる。
証拠の確保~客観的な記録を残す
カスハラ対応において、適切な証拠を確保することは極めて重要だ。証拠は、後の対応や法的措置において事業者や従業員を守る役割を果たす。具体的には、以下の方法が挙げられる。
●録音や監視カメラの映像
可能な範囲で録音や映像記録を取ることで、トラブルの内容を客観的に記録する。これにより、カスハラ行為の詳細を正確に確認でき、問題がエスカレートした場合にも有効な証拠となる。
●記録の徹底
責任者や従業員が、カスハラ発生時の状況をメモに記録することも有効だ。日時や場所、加害者の言動、対応の経緯などを詳細に記録することで、事後の検証がスムーズになる。証拠の確保は、従業員を守るだけでなく、事業者が正当な対応を取るための基盤となる。日頃から記録を徹底する習慣を持つことが重要だ。
外部機関との連携:専門家や警察の協力を得る
カスハラの内容が悪質な場合、事業者だけでの対応が難しくなることも多い。この際は、外部機関と連携して解決を図るべきだ。
●弁護士や専門家への相談
カスハラ行為が法的問題に発展する場合、弁護士への相談が必要となる。法律の専門家と連携することで、事業者側が適切な対応を取れるようになる。特に名誉毀損や暴行、威力業務妨害に該当する場合には、早期の相談が推奨される。
●警察への通報
暴力行為や脅迫行為などが発生した場合は、直ちに警察へ通報する。警察の介入により、事業者や従業員の安全を確保するとともに、問題行為を抑止する効果も期待できる。外部機関との連携は、事業者と従業員の双方を守るために有効な手段といえる。一人で問題を抱え込むのではなく、適切な機関に支援を求める姿勢が重要だ。
従業員のケア~心身の健康を守るサポート
カスハラを受けた従業員へのケアも重要な対応策の一つだ。精神的なダメージを負った従業員がそのまま業務を続けると、さらなるストレスや離職の原因になりかねない。ガイドラインでは、以下のようなケアが推奨されている。
●相談窓口の設置
従業員がカスハラについて相談できる内部窓口を設ける。話を聞くだけでも従業員の安心感につながり、問題を共有する環境を作ることができる。
●専門機関の活用
必要に応じて、産業医や心理カウンセラーなど専門家のサポートを受けさせる。これにより、従業員の心身の健康を維持し、職場への信頼感を高められる。また、職場環境の改善や企業全体のイメージ向上にもつながるだろう。
再発防止策~予防のための体制整備
カスハラ対策は事後対応だけでなく再発防止の仕組み作りが欠かせない。事業者には以下が求められる。
●従業員教育の実施
カスハラ発生時に適切な対応が取れるよう、従業員に対する研修を実施する。研修では、顧客対応スキルやクレーム対応の基本を教えるとともに、カスハラに関する具体的な事例を紹介することで実践的な知識を身に付けさせる。
●対応マニュアルの整備
カスハラが発生した際の対応手順をマニュアル化し、従業員が迷うことなく、迅速かつ適切に行動できる体制を整える。責任者への報告方法や、警察や外部機関への連絡フローなどを明確にしておくと効果的だ。
●職場環境の見直し
従業員が働きやすい環境を整えることで、カスハラへの耐性を高める。例えば、従業員同士が連携しやすい仕組み作りなど、孤立を防ぐことが重要だ。
全国のカスハラ防止条例の動向と東京都との比較
東京都以外の自治体でもカスハラ防止に関する動きが進んでいる。北海道と三重県桑名市は、2025年4月にカスハラ防止条例を施行予定であり、それぞれの条例内容や特徴には違いがある。ここでは、東京都の条例と比較しながら全国の動向を解説する。
北海道のカスハラ条例~観光業を守る対応策
北海道は観光業が盛んなため、観光客からのカスハラが問題となることが多い。また、外国人観光客と接する機会が多いため、言語や文化の違いから生じる不当な要求やトラブルが発生しやすい。こうした地域特性を踏まえ、条例では業種や業態に適した施策を市町村と協力して進めることが明記されている。
また、道は事業者が活用できる指針を策定する予定だ。この指針には観光施設や宿泊業、飲食業といった地域産業に特化した具体的な対応策が盛り込まれることが期待されている。
三重県桑名市のカスハラ条例~氏名公表で再発防止へ
桑名市の条例案では、悪質なカスハラ行為者の氏名など特定可能な情報を公表する措置が盛り込まれたことで注目が集まった。この案は従業員を守るだけでなく再発防止や抑止効果を狙ったものだ。
氏名公表には慎重な手続きがある。まず、市長が行為者に警告を行い、それでも状況が改善されない場合にのみ実施される。さらに、公表に先立ち行為者に意見を述べる機会を与えるほか、市長は委員会の意見を参考に判断する。こうした手続きで不当な氏名公表が防がれるよう配慮されている。
他の自治体の動向
東京都、北海道、桑名市以外の自治体でも、カスハラ防止条例の制定に向けた議論が広がっている。特に、人口が多い都市部や観光業が盛んな地域は顧客とのトラブルが深刻化していることから、飲食業や宿泊業の従業員を中心にカスハラへの対応策を求める声が高く今後同様の取り組みが進む可能性が高い。
また、国レベルでのカスハラ対策も注目されている。厚生労働省をはじめとする関係機関では、全国的な統一基準が示されるガイドラインを整備する計画が進行中だ。このガイドラインには、
●自治体ごとの対応格差を解消
●カスハラ問題に対する社会全体の意識改革を促進
●企業が従業員を保護するための指針を得やすくなること
などが期待される。今後、地域特性に応じた条例の制定と全国的な基準の整備が進むことで、カスハラ問題の解決に向けたより包括的な取り組みが実現するだろう。
事業者によるカスハラ防止の取り組みが必要
カスハラは被害を受けた従業員だけでなく、周囲の顧客や従業員、経営全体に悪影響を及ぼすため、カスハラ対策は経営戦略上必須の課題といえる。事業者はこれらの条例やガイドラインを活用し、従業員を守る体制を整えるとともに、顧客と従業員の信頼関係を築いていくことが求められる。カスハラ問題は社会全体で取り組むべき課題であり、行政、事業者、そして消費者が一体となって、安全な環境を作ることが重要だ。