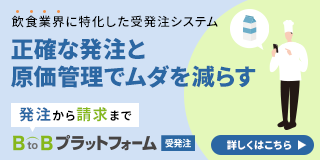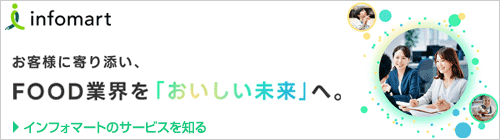セントラルキッチンとファームの誤算と真の価値
トラジの成長と味の均一化を支えてきたのが、江東区新木場にあるセントラルキッチン(CK)である。ここでは肉の加工のほかタレや漬物などを製造している。導入当初の目的はコストダウンと味の標準化であったが、金氏は経営者として意外な事実を口にした。
「結論から言えば、CKによるコストダウンにはあまり繋がっていない。より良い食材、より高い技術を求めていくと、むしろコストは上がるのが現実だ」
同様のことは、自社で牛を一貫肥育する「トラジ・ファーム」にも言える。子牛価格の高騰に対するリスクヘッジとして始めた試みだが、外部から仕入れるのとコスト面では大差なく、むしろスタッフの教育コストなどは増大しているという。
それでも金氏がこれらを維持し続ける理由は、数字には表れない独自性とブランドの魂にある。
「他社に外注すれば安く済むかもしれない。しかし、自分たちの味は自分たちで作りたいという『母心』のようなこだわりが、ブランドの根幹になる。効率を逆行してでも自分たちでやる。これが勝ち組と負け組みを分ける境界線になるのではないか」
人手不足時代を突破する、薬剤師のような接客
深刻化する人手不足についても、金氏は鋭い持論を展開した。時給アップや採用媒体の強化といった仕組みの対策には限界がある。今、必要なのは従業員がその店で働く意味と思いを共有することだという。
金氏が提唱するのは、店舗における個別対応(パーソナライズ)への回帰である。
「これからの職人は、薬剤師が患者に処方箋を出すような接客をすべきだ。お客様の予算やその日のコンディションに合わせ、『今日はこの肉をこう食べましょう』と個別に提案できる。単にメニューを並べて注文を待つだけの店は、今後淘汰されるだろう」
セントラルキッチンでベースとなる味を標準化しているからこそ、現場のスタッフは最後の仕上げやお客様との深い対話にエネルギーを注げる。作業としての労働ではなく、顧客の心に刺さる仕事へと昇華させることが、従業員のやりがいと顧客満足を両立させる唯一の道だと説いた。
実食から始まる、心に残るサービス
現場力を高めるための具体的な取り組みとして、金氏は実食の重要性を強調する。
「最近はスタッフに、おすすめを言う前にまず実食しようと伝えている。食べたこともないものを売るのはおかしい。自ら食べて感じた言葉でお客様に伝える。そんな『血の通ったサービス』こそが、今の時代に求められている」
また、焼肉店では軽視されがちなデザートやワインについても、食後の余韻を作る重要な要素として注力している。社内ワインソムリエ制度を設け、100名以上のスタッフが取得しているのもその一環だ。
焼肉は、味も栄養も王様——30年目の決意
1995年12月、恵比寿の小さな店舗から始まったトラジ。2025年12月には創業30周年を迎える。「焼肉は味も栄養も王様である」という理念は、今も揺らぐことはない。
金氏は最後に、会場の飲食経営者たちに向けてこう締めくくった。
「今は店舗過剰の厳しい時代。しかし、そんな時こそシンプルに考えよう。従業員を大切にし、食材にフォーカスし、お客様を喜ばせる。自分たちが何のために集まっているのかを、情熱を持って伝え続けること。そこに近道はない」
トラジ(桔梗)の花言葉どおり、根を深く張り、価値を提供し続ける。金氏の挑戦は、焼肉という枠を超え、成熟期に入った飲食業全体の進むべき指針を示している。