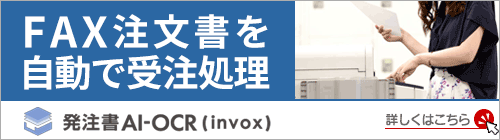兵庫県加古川市の「肉のまちづくり推進協議会」は、精肉文化と和牛の魅力を体感できる観光ツアープログラム「神戸牛しゃぶしゃぶを含む加古川和牛文化体験」を2025年4月21日(月)より販売開始いたしました。

肉のまちツアー_精肉加工見学の様子
本ツアーでは、加古川食肉市場での模擬競りや解体見学、職人によるカット体験、神戸ビーフを 使用した「肉ケーキしゃぶしゃぶ」ランチなど、普段触れることのない“肉の現場”を体験していただけます。
兵庫県の「ひょうごフィールドパビリオン SDGs体験プログラム」に認定されており、株式会社エイ チ・アイ・エス (H.I.S. Co., Ltd )との連携のもと、国内外の旅行者に向けた高品質な体験型ツーリズムとして展開されています。(予約サイト: https://hisvisitjapan.com/ja-JP/product/B-0605)

ひょうごフィールドパビリオン ロゴ
■ 和牛と肉職人の“リアル”にふれる特別な1日
但馬牛の素牛を扱う神戸ビーフの出荷拠点・加古川は、150年以上の歴史を持つ“精肉のまち”。 本ツアーでは、食肉の流通・加工・提供の裏側にある職人たちの技術と誇りを、体験を通じて深く知ることができます。

肉のまちツアー_せり体験の様子

肉のまちツアー_捌き見学の様子

肉のまちツアー_加古川食肉センター入口
・加古川食肉センターにて模擬競り体験
・大樹商店にて精肉職人による枝肉カット見学
・肉のヒライにてプロの指導のもと、実際に肉をカット体験
・Sabo1538 神戸ビーフ使用「肉ケーキしゃぶしゃぶ」ランチ
いずれも、地元の専門事業者・職人の皆さまの協力のもと実施。和牛文化を支える現場に実際に足を運び、技と誇りを感じていただけます。
■世界記録に輝いた“肉ケーキ”で味わう神戸ビーフ
ランチには、神戸ビーフを贅沢に使用した「肉ケーキしゃぶしゃぶ」をご提供。
この肉ケーキは2024年9月20日(金)に、地域の精肉店など食肉関係事業者をはじめとする約30社・50人以上の協力により約4時間かけて製造され、翌日21日に兵庫県加古川市で開催された「JAPAN BEEF FESTIVAL」の会場内でその場に立ち会ったギネス世界記録認定員により「最大の生肉ケーキ/ Largest raw meat cake」としてギネス世界記録(TM)?に認定されたことを受け、開発された特別メニューです。見た目のインパクトと味わいの奥深さがSNSやメディアでも 話題となっており、記憶に残る一皿としてツアーの締めくくりを彩ります。

肉のまちツアー_神戸牛肉ケーキ
■ 産業×観光×教育でつくる、持続可能な“食文化体験”
本ツアーは、精肉職人の技術を“見て・学び・体験する”ことで、食の現場への理解を深めるだけでなく、職人の社会的評価の向上や若手人材の育成にもつながる取り組みです。すでに日本食材の地産外商や地方創生に取り組む企業による視察やメディア取材の実績もあり、地域の産業と観光をつなぐモデルケースとして展開されています。今後も地域の魅力を体験型コンテンツとして発信し、旅行者の来訪動機の創出や持続可能な地域観光の実装を目指してまいります。

肉のまちツアー_せり体験の様子
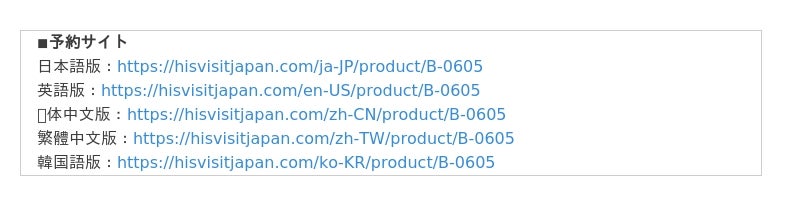
詳細を見る
■ 大阪・関西万博会場にて開催の「ひょうごフィールドパビリオンフェスティバル2025」に出展いた します!
本ツアーの魅力をより多くの方に知っていただくため、このたび、肉のまちづくり推進協議会は、 2025年5月29日(木)に大阪・関西万博会場で開催される「ひょうごフィールドパビリオンフェスティバル2025」(主催:兵庫県)への出展が決定いたしました。会場は、万博催事場「ギャラリー WEST」屋外展示スペースです。
当日は、世界記録を達成した“肉ケーキ”や肉職人の技を伝える体験ツアーのご紹介、和牛肉の 試食提供などを通じて、和牛の奥深さと地域産業の魅力を体感いただけます。現地では、ツアー で訪れる精肉現場の様子や地域の取り組みもご紹介予定。五感で味わう“肉のまち加古川”を、 ぜひ会場でご体験ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
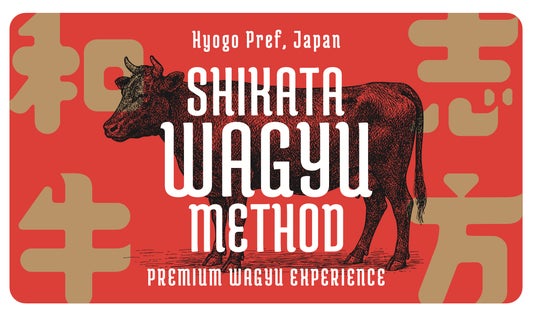
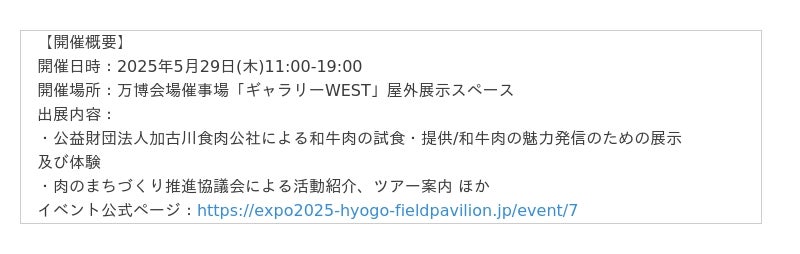
■ 肉のまちづくり推進協議会とは?
肉のまちづくり推進協議会(兵庫県加古川市)は、「肉屋をもっとカッコよく」をコンセプトに、精肉
職人の技や和牛文化といった日本独自の食の魅力を、国内外に広く発信することを目的に2024
年に発足しました。地場産業である“牛肉”に光を当て、「肉まちづくり」を進めるとともに、職人文化の継承と地域経済の活性化を両立させる取り組みを展開しています。地元の生産者や精肉業者・食肉関係団体等食肉産業をはじめ食を通じた地域創生に関心を持つ企業・団体との連携のもと、フードフェス「JAPAN BEEF FESTIVAL」やツアー、教育機関等での講座、ギネス世界記録(TM)プロジェクトなど、消費者と直接つながる機会を創出し、食肉業界の新たな価値提案に挑戦しています。