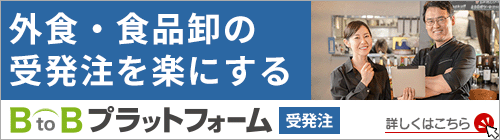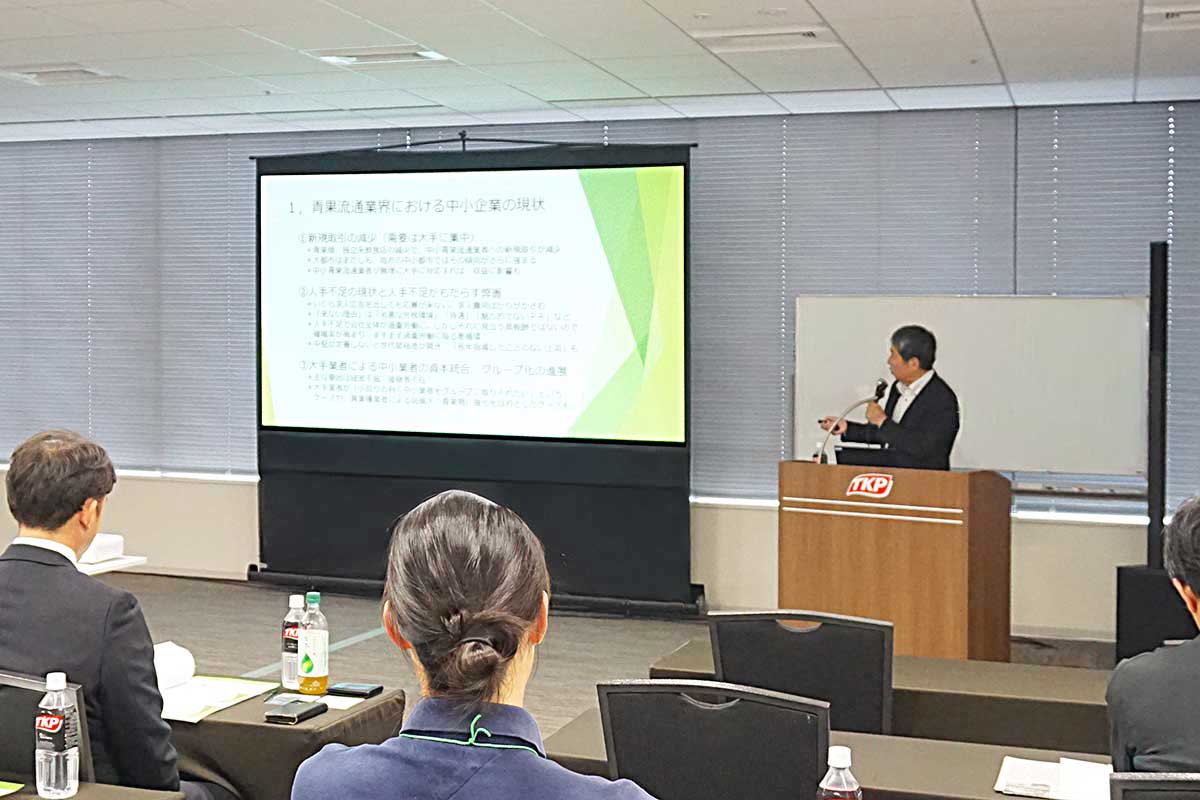この度、一般社団法人バックオフィスプロフェッショナル協会(代表理事:木村仁哉)は、バックオフィスの主要領域である、経理財務・人事労務・法務総務に加え、ITリテラシー・コンピテンシーを加えた計5つの領域におけるスキルを包括的に測定する検定「バックオフィスプロフェッショナル検定」を開発いたしました。当検定により、バックオフィス業務のスキル水準を可視化し、企業の人材採用や社内評価に向けた新たな判断基準としての活用を目指します。
検定開発の背景
近年、バックオフィスに関する様々なシステムの登場や業務の自動化により、バックオフィス業務に求められるスキルが変化しています。これまでは、会計・労務・法務など、各部署において高い専門性を有していることが重視されていました。しかし、例えばクラウド会計ソフトが、給与計算・社員の入退社・経費精算などを管理する他のシステムと連携する機能が充実し、各方面の情報を取り込むことが一般的になりつつあります。さらには、RPAやAIの発達や、生産人口の減少といった背景から、バックオフィスの担当者は一人で複数の領域をまたいだ、広範な知識とスキルが求められる時代へと変化をしています。
このような中で、バックオフィスの全体像の理解の深さによって、生産性に非常に大きなバラつきが見られるようになっております。しかしながら、バックオフィスの全体像やこれら多領域にわたるスキルを問う検定がこれまで存在していなかったことから、企業側はバックオフィス人材がその理解の程度を図る手段がなく、一方のバックオフィス人材側も、自身のバックオフィスのスキルを高めていくためのステップが存在しておりませんでした。このような背景から、バックオフィスプロフェッショナル検定を開発するに至りました。当検定を普及していくことにより、企業のバックオフィスにおける生産性の向上に貢献しつつ、バックオフィス人材のスキルアップの道しるべとなっていきたいと考えております。
検定の構成・内容
問題数:全100問
回答時間:90分
設問範囲: 経理財務、人事労務、法務総務、ITリテラシー、コンピテンシーの5領域
形式: 選択式と記述式
実施方法: オンライン

第1回検定を下記の要項で開催いたします。
第1回検定
試験実施日:2025年6月8日(日)
申込締切日:2025年5月11日(日)
お申込み:https://bpo.hp.peraichi.com/exam
※第2回検定は2025年10月、第3回検定は2026年2月を予定しております。
検定の構成は、1.正しい数字や単語を選択する問題、2.4択の中から正解を選択する問題、3.複数の領域にまたがり応用力を試すための記述式問題の3部から成ります。
バックオフィスの主要領域とITリテラシー・コンピテンシーの計5つの領域を総合的に測定することで、バックオフィス全体を見渡す能力を培います。また、知識を測ることに加え、思考や行動特性といったマインド面の評価も含まれており、実務で活躍できる人材を見極めることも可能です。
評価方法は、合否を判断するのではなく、各領域における理解度を点数または5段階で表示する方式です。自身の強みを確認できるとともに、理解を深めるべき領域の発見など、将来の目標に向かって何度も受験に挑戦して欲しいという想いを込めてこの方式を採用いたしました。
検定のサンプル問題
下記のように、バックオフィスの各領域を「浅く・広く」問うことで、バックオフィスの全体像の理解度を測定します。
1. 法人は、決算日から___以内に法人税等の申告書を提出し、期日までに納税する義務がある。
答え:2か月
2. 売上高100万円、売上原価60万円、人件費20万円、支払利息10万円のとき、粗利益はいくらか。
答え:40万円
3. 時給1,000円のスタッフに1日8時間を超えて労働させた場合、8時間を超えた部分の1時間あたりの給与はいくら以上支払う必要があるか。
答え:1,250円
4. 社会保険と雇用保険の届出は、___というシステムを利用した電子申請が推奨されている。
答え:e-GOV
5. 秘密保持契約のことを、略して___という。
答え:NDA
検定の出題範囲と監修
検定の出題範囲は、前述のとおり経理財務・人事労務・法務総務・ITリテラシー・コンピテンシーの5つの分野となります。また、当検定の公式教材として、植西祐介氏の「バックオフィス業務のすべてがわかる本」(日本実業出版社)を採用しております。
植西祐介氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士の3つの資格を保有し、大手メーカー・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験を持ち、さらには自身での事業開発に加え、YouTubeを通じた発信を行うなど、広範な活動をされています。氏の著書である「バックオフィス業務のすべてがわかる本」においてはバックオフィスの全体像の重要性を指摘し、その全体像を描いた氏の功績は大きく、当協会の活動理念と重なる領域が大きいことから、当検定の監修を依頼しております。
「バックオフィス業務のすべてがわかる本」
植西祐介氏・著
日本実業出版社
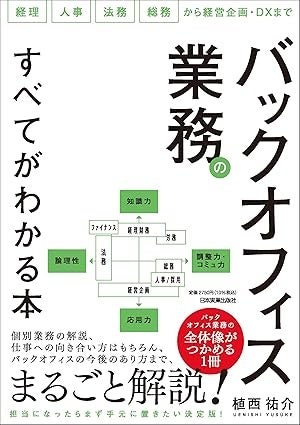
検定を受けるメリット
当検定は、企業側がバックオフィス人材を採用する時の判断基準としての使用だけでなく、企業内部での従業員のスキル測定にも活用いただけます。面接では測りにくいバックオフィス業務のスキルを、検定を通して可視化することで、採用の円滑化、また企業の業務効率化と人材育成を支援することを目指しています。
また、人材側においても、これまで示されていなかったバックオフィス人材のキャリアアップの道しるべとなり、いま企業から求められる領域と、各領域における自身の理解度を知る機会となります。
企業へのメリット:
- バックオフィス人材の採用時の客観的な評価基準となる
- 社内におけるバックオフィス人材のスキルの可視化が可能となる
- バックオフィス業務の効率化に向けた人的リソースの測定が可能となる
個人へのメリット:
- すべての事務職のキャリアアップの道しるべとなる
- 自分のスキルを客観的に把握できる
- バックオフィスや事務職の人材市場における自身の立ち位置の明確化が可能となる
この革新的な検定を多くの企業様に認知・採用いただき、バックオフィス業務のスキルの判断基準とすることで、バックオフィス業務の更なる効率化と発展に貢献して参ります。
バックオフィスプロフェッショナル協会について
一般社団法人バックオフィスプロフェッショナル協会は、BPO事業に取り組む事業者の経験・ノウハウ・情報の調査と共有を推進することにより、BPO事業者のサービス品質並びに経営状態を改善し、BPOサービスを通じてクライアント企業を支えることによって、日本経済の発展に貢献することを目的としています。
※BPOとは
Busuiness Process Outsourcing(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の略で、自社の業務を外部に委託する取引です。事務や経理といったバックオフィス業務やWEB制作といったクリエイティブ業務など、外部の専門とする企業に委託することで本業へ集中する時間を確保すると共に、業務品質の向上やコスト削減が期待できます。
【協会概要】
会社名:一般社団法人バックオフィスプロフェッショナル協会
代表理事:木村 仁哉
設立 :2023年11月
URL :https://bpo-pro.org/
詳細・お問い合わせ
当検定に興味を持たれた企業さまや、ご自身のバックオフィス業務の能力を測りたいとお考えの方は、以下のリンクよりご確認・お問い合わせください。
https://bpo.hp.peraichi.com/
一般社団法人バックオフィスプロフェッショナル協会
一般社団法人バックオフィスプロフェッショナル協会は、BPO事業に取り組む事業者の経験・ノウハウ・情報の調査と共有を推進することにより、BPO事業者のサービス品質並びに経営状態を改善し、BPOサービスを通じてクライアント企業を支えることによって、日本経済の発展に貢献することを目的としています。